
音響設計と音場シミュレーション技術
-音場の可視化から可聴化へ-
音響設計と縮尺模型実験
室内音響設計にあたって、1/50~1/10の縮尺模型を製作し、音響特性をチェックしながら室の形状、壁や天井の詳細を検討してゆく手法が確立してから約40年になる。この音響模型実験は音響設計の先端技術を象徴する作業として脚光をあびた時代もあった。しかし、この手法は模型製作にコスト(2000席クラスのホールの1/10のラフな模型で約2000万円)と時間(設計と製作に約2~3ヶ月)がかかり、実験にも短くて3ヶ月、場合によっては6 ヶ月以上という時間を必要とする。そもそもスケジュール的に余裕のない建築設計段階に、模型実験だけでこのような時間を組み込む事など殆ど不可能だというのが現状である。
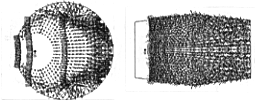

また、現実的な問題として1/10の模型を置くスペースの確保がある。それよりも、1/10の模型が製作できるのは設計がかなり進んだ段階であり、模型実験の結果を待って基本形状を変更することなどは不可能だという根本的な問題がある。ヨーロッパでも模型実験が終わった頃にはホールが完成していたという笑い話しもあるほどである。たしかに、模型実験はデモンストレーションとしての効果は否定できないが、基本計画段階における室形状の検討といった、重要で、しかも短時間に方向を決めなければならない実質的な作業は次に示すコンピューターシミュレーションにとって替わっている。
コンピューター・シミュレーション(CS)による音場の可視化(visualization)
CSには鏡像法と音線法とがある。音線法とは音源を多数の音線で代表させ、壁や天井で反射する音線の一つ一つをコンピューターで追跡し、客席内に到達する音線の分布を求める手法である。図は初期反射音分布から好ましいとされる形状のホールと、円形の平面をもつホールの初期反射音分布の比較である。分布の違いは視覚的にも明らかで、このような手法を音場の可視化(visualization)
という。現在、この手法は基本設計段階において室の形状の設計の有力なトゥールとして定着している。
しかし、問題はその評価基準である。われわれはまず、国外の著名なホール、および実際のコンサートをとおして響きの特徴を聴感的に把握している都内のホールにこの手法を適用し、好ましい条件を検討した。反射音分布からみたウィーン楽友協会ホールの特色、身近な例では東京文化会館大ホール5 階席の特色、サントリーホールの一階席と二階席の違いなどから図形の判断基準を固めたのである。しかし、音源を音線の集合として扱うこの手法には当然限界がある。最近竣工した紀尾井ホールと京都コンサートホールはいずれもシューボックス型のホールであり、その反射音分布は図形でみる限りよく似ているが、演奏をとおして感じる響きの印象は異なるのである。現在のCS手法も決して万能ではない。ホールの響きについてはいろいろな視点からの解析が必要なのである。
しかし、このCSはホールの形状の入力に多少の手間がかかるが、音響効果に関連する初期反射音についての情報を手軽に得られる点で、基本計画段階の室形の検討には欠くことのできない手法である。一方模型実験は、実施設計段階における壁や天井の意匠と音響特性との整合性の検討、聴感実験によるエコーのチェックなどの目的に使用している。
音場の可聴化(auralization)
音響模型実験はもともと音場の物理特性の測定だけではなく、“模型をとおしてホールの音を聴く事ができる”という機能を特徴として開発された手法である。しかし、1/10の模型では10倊の周波数帯域での信号音をあつかうため、スピーカ、マイクロホンの性能の限界、周波数変換部のS N などから模型をとおした音は、初期の段階では評価実験の対象になるような代物ではなかった。今では信号処理技術の発達から、無響室録音の音源さえあれば、それと模型音場の特性( インパルス・レスポンス) を信号処理によって掛け合わせ、模型をとおしての音をかなりの品質で聴くことができる。いや、高価な模型を製作しなくても、音場の特性さえ分かれば同じ手法で音を聴くことができる。これを音場の可聴化 (auralization)という。
いま、この可聴化は室内音響研究でもっとも話題をよんでいる分野であるが、設計の実務に用いるには根本的な問題がある。それは、音源の問題と評価実験における判断基準である。点音源とみなせる楽器、無響室で録音できる楽器、たとえば、人の声やフルートなどは自然であり、場所による響きの違いなども明確に聞き分けることができる。無響室におけるオーケストラ録音もCDとして発売されているが、この音質でどの程度の評価実験ができるのだろうか、疑問である。たとえ、高品質の音が再生できたとしても、これはあくまでスピーカをとおしての音の再現である。
人工音場による評価実験

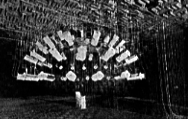
ホール空間のシミュレータとして、響きのない空間に多数のスピーカを立体的に配置し、残各スピーカから残響音や反射音を放射させるという仮想空間が考えられる。このアイディアによる装置は、すでに1960年代に旧西ドイツ、ゲッチンゲン大学の音響研究室で具体化し、代表的なホールの音場が再現されていた。次ページの図はKuttruff教授の著書 Room Acoustics に紹介されている装置である。当時、この音響研究所では故E.Meyer 教授の指導のもとに、複雑なホールの反射音をどこまで省略して人工音場を構築することができるか、という課題を目標に、反射音と聴感との関係についての組織的な研究に着手しており、これが今日の室内音響研究の原流となった。
しかし、当時の最大の課題は遅延装置であった。ここでは、たしか、秒速190cmのループ状のマグネチックテープに多数のヘッドを配置した特殊なテープレコーダが使用されていた。しかし、現在では信号処理技術によって、信号音の遅延も残響付加も自由であり、方向情報を含む反射音による音場が合成できる。
無響室を占拠するこの装置はわが国では大学や音響研究部門をもつ大手企業の実験室には必須の設備(別名:鳥籠)として導入され、評価実験に使用されている。一方、ヨーロッパではむしろ、ヘッドフォンやスピーカを用いた試聴方式の開発に関心が向いているようである。たしかに、拡散体の効果など今後の音響効果の研究は、この人工音場によらざるを得ないであろう。そのためにこそ、音響効果の判断基準という大きな壁を克朊しなければならない。
音響設計の実務に使用できるBose社のAuditioner
スピーカなどユニークな製品を次々と市場に送りだしているボーズ社が画期的ともいえるシミュレーション装置‘Auditioner ’を開発した。これはあくまで、拡声設備をとおしてのスピーチの聞こえ方を耳で確認するという目的に絞った装置である。右図のようにコンパクトで設計の現場に持ち込むことができる。音を聴くには左右の小型スピーカの間に顎をのせるだけでよい。方向情報も完全ではないがかなりリアルである。筆者もある体育館について試みてみたが、吸音の程度による明瞭度の変化、スピーカーの機種、数、設置場所を変更したときの聞こえ方の違いなども簡単に確認できる。音場条件の取り込み方などかなり単純化したようであるが、ボーズ社の製品に一貫するこの割り切り方が見事である。とかくデモ的な性格に傾きやすいこの種の装置を設計の実務に使用できる製品としてまとめた事は模型実験から始まったシミュレーション手法の一つの金字塔として評価できる。音楽ソースへの拡張が今後の課題である。(永田穂 記)
京都コンサートホールステージまわりの音響実験
このホールのステージには、電動のオーケストラ迫りや竪リブの背後空間など調整できる箇所が設けてあり、竪リブ裏は木製のパネルで塞いだ状態でスタートしたことを以前のNewsで紹介した。オープニングシリーズが一段落した3 月28日、指揮者井上道義氏の強い希望により、リブ底の薄いネットを外し、さらにリブ裏の空間やリブの前に内倒しの反射面を仮設的に作って、その変化(効果)を実際の演奏で確認する実験を行なった。16型編成(1st.Vn.16 、2nd.Vn.14 、Vl.12 、Vc.10 、CB8 +管・打楽器)の京都市交響楽団のベートーヴェンの交響曲第5 番ほかのリハーサルを対象に評価実験が行われた。今回の実験はかねてから本ホールの響きについて“指揮台のところでもっと酔いたい”、“もう少し醍醐味がほしい”といわれていた井上氏の要望に応えて行われたものである。
筆者は本実験の直前の状態を確認していないが、今回の実験では、いずれの条件においても、劇的な変化は認められなかったようである。しかし、以下の範囲で、微妙な響きの違いが確認できた。
- 音響的に透明な素材とみなせるネットの有無による違いは殆ど無かった。
- 上手側の内倒した反射面によって、 弱めの中・低弦の音量が増す効果があることが確認された。
- 下手、正面の反射面については、逆にオーケストラのバランスが崩れるという印象であった。特に、リブ前に内倒しの反射面を設定した場合(写真)には、ホールの空間イメージが薄れてやや圧迫感のある鳴り方が感じられた。

仮設の反射板
それよりも、今回の実験で何よりの驚きは、空席状態、ベートーヴェンの作品という条件のもとでの演奏ではあったが、最初に出た音から、ホールが”鳴っている”印象を強く感じたことである。ステージまわりの条件を変えることで、響きに微妙な違いが生じることは上記のとおりだが、これは、ホールの鳴り方が本質的に変わるという印象ではなかった。久しぶりに聞いた我々にとっては、ホールの鳴り方がオープン初期に比べてかなり変わってきていることの方がインパクトが強かった。その変わり方は、井上氏の言う”醍醐味”が増す方向への好ましい方向への変化であると思っている。これは、最も演奏回数の多い京響がこのホールと一体となって、この空間にふさわしい音作りに集中してきたことが大きな要因ではないだろうか。一方、短い期間ではあるが、エイジングによる響きの変化も否定できない現象だと思う。実験後、リブ底のネットは復旧したが、その裏は井上氏の意向で合板を内倒しに立てかけた状態にセットしてある。この状態でバランスやアンサンブルがどのように変わってゆくのか、その確認にはしばらく時間が必要であろう。
オープン以来半年を経ただけであるが、演奏者、我々の慣れまでも含めてホールの響きは確実に好ましい方向に変化してきている。これまで、サントリーホール、その他のホールにおいても、こうした変化がほぼ収束するのに5 年程度かかっていることを考えると、ここでも我々は慎重に経過を見守ってゆく立場をとりたい。以前紹介したように、客演演奏家からも同様な意見が数多く寄せられている。(小口恵司 記)
News100号記念の集いのご案内
本Newsも今月で発刊100 号になります。これを記念して、6 月8 日(土) の午後、津田ホールにおいて、礒山雅氏(国立音楽大学教授)の講演、テーマは「現在のホール、未来の聴衆」と、モーツァルトのクラリネット五重奏曲(独奏:四戸世紀氏他)の演奏を中心に、皆様との歓談の一時を持ちたいと考えております。詳細は次号でお知らせいたします。