ふくやま芸術文化ホール(リーデンローズ)オープン
広島県の福山市が建設を進めていた「ふくやま芸術文化ホール」がこの度完成し、去る11月2 日に地元の広島交響楽団の演奏でオープンした。福山市は岡山市と広島市との中間に位置する人口約32万の地方中核都市で、昭和41年にすでに1500席規模の市民会館を建設している。芸術文化ホールはこの市民会館に代わる新しい芸術文化の拠点として約2000席の大ホールと約300席の小ホールを中心に構成された施設である。この二つのホールはいずれも音楽を主目的とした多目的ホールであるが、当初の計画では、さらに演劇を主目的とした約700席の多目的ホールが予定されていたが、予算の関係から、まず大・小ホールのみの建設となった。建築設計は(株)日本設計の関西支社である。
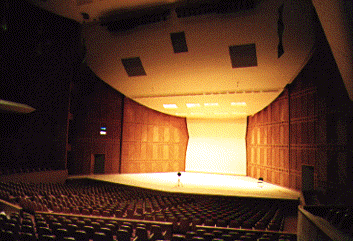
ホールには「リーデンローズ」という愛称が付けられている。これは、市内を流れる芦田川(葦田川)の葦(Reed)と市の花であるバラ(Rose)に因んだもので、 Reed & Rose(リード・アンド・ローズ)が訛ったものである。
リーデンローズの大きな特長は大ホールにある。音楽を主目的とした多目的ホールであるが、シューボックス型ではなく、六角形を基本的な平面形状として採用している。設計にあたっては東京文化会館の大ホールを範として検討を進めた。この会館の設計そのものはかなり古いものの、当時のNHK技術研究所が総力を挙げて音響設計に取り組んだだけあって、初期反射音が効率よく得られるような形状の検討が丹念になされており、最新のコンピュータ・シミュレーションによる解析結果からもそのことは明らかであった。ご存じのように東京文化会館は完成後、長らくクラシック音楽の殿堂としての役割を果たし続け、周囲にクラシック用コンサートホールが増えてきた今日でもその音響の良さが高く評価されている。しかし、最近のコンサートホールに比べると響きが短めで、多少ドライに感じることも否めない事実である。福山の音響設計にあたっては、その初期反射音に関する形状の利点を生かしながら、より豊かな残響音を実現することに努めた。
東京文化会館を範としたもう一つの大きな特長は、クラシックコンサート時にオーケストラピットを上げてステージの一部として使用することを前提としていることである(上図参照)。この方式の利点は、ステージ上の天井高が多目的ホール特有の低いプロセニアム開口の制限を受けない点にある。多目的ホールにおけるステージ天井高がプロセニアム開口によって低く押さえられることは、音響反射板設置時のホールの室内音響特性に対してかなりの制約を与えており、これは多目的ホールが抱える大きな問題点の一つでもある。最近の多目的ホールでは可動型のプロセニアム開口を導入する等の工夫によりこれらの改善を図っているが、オーケストラピットを利用してコンサート時のステージを前に引き出すことによっても、プロセニアム開口の制限を受けないでステージ天井高を高くすることが可能となる。ほかに、ステージ音響反射板のピースが小さく、かつ少なくてすむなどもこの方式の利点である。一方で、音響反射板設置時には客席数がやや少なくなるという欠点も合せ持っているが、福山においてはクラシックコンサート時の客席数として必ずしも2000席必要ではないということもあって、この方式の導入が可能となった。このケースでは、客席数最大2003席に対してクラシックコンサート時は1831席となり客席数が約1割少なくなる。
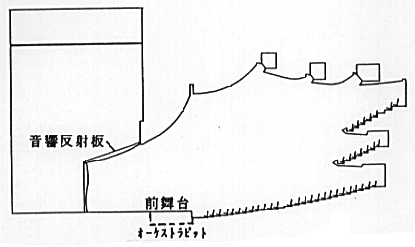
東京文化会館のように多層バルコニーを持つ六角形のホールとしての特長は、建築設計の上でも生かされている。すなわち、1階メインフロアの客席のレベルや向きをいくつかのブロック毎に変化を持たせて配置することによって、ホール客席内における一体感、賑わいなどが感じられるように工夫されている。さらに、2~3階のバルコニー席についても客席によって角度を変えて配置することにより、1階席と合わせてホール客席全体の雰囲気作りに役立っている。従来の多目的ホールにおいては、視線確保という機能優先の観点からあらゆる客席をステージに正対して一方向に配置するのが一般的で、客席内の雰囲気作りの点ではいまひとつの感がある。最近では、ステージから客席への一方通行ではなく、客席同士やステージと客席との一体感がより感じられるホール空間づくりが志向されており、アリーナ型、ワインヤード型といった客席配置のコンサートホールや馬蹄形のオペラハウスが注目を集めたり、小型ホールにおけるサイドバルコニーの設置も積極的に試みられている。
音楽を主目的としたリーデンローズ大ホールは、可動型のステージ音響反射板のほか客席側壁の一部にもカーテン開閉方式の簡易な残響可変装置を備えている。残響時間の測定結果は 2.0~1.6秒(500Hz、満席時)であった。オープニングの広島交響楽団(十束尚宏指揮)に引き続いて翌日のモスクワ国立交響楽団の演奏を聴いた印象は、ホール全体がよく鳴り響く感じで専用のコンサートホールに対して優るとも劣らないといっても過言ではない。もっとも、どの様な演奏でもきれいに響くわけではなく、演奏のクォリティの良し悪しも、よりストレートに明らかになり、ある程度レベルの高い演奏が求められる点もコンサートホール同様である。
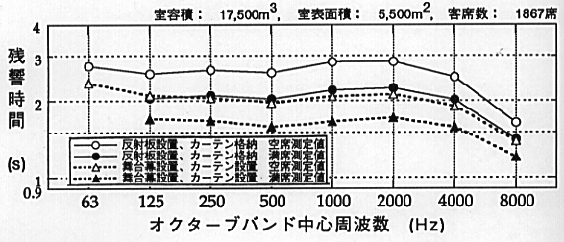
新しいホールの敷地は福山駅から歩くと25~30分程かかる所にあり、旧市民会館が10分程の所であったのと比べるとやや交通の便が悪い。周辺は昔からの工場なども点在しており、文化ホールの環境として必ずしも相応しいとはいえない場所である。ホールの建設はこの地域の再開発計画の一環として位置付けられているものの他の開発計画が遅れており、とりあえずホールのみが建設されたという状況にある。また、今回建設が延期された中ホールはその規模から最も使いやすく重宝されると考えられる。中ホールの建設と周辺環境の早期整備が望まれる。ホール見学、コンサートなどの問合せ、連絡先は福山リーデンローズまで。(TEL:0849-28-1800)(豊田泰久 記)
NEWSアラカルト
パレストリーナ、ラッスス400年記念連続コンサート
今月の13日(日)の午後、東京杉並のカトリック下井草教会において、表記のコンサートが行われた。このコンサートは1594年になくなったルネッサンス時代の二人の音楽家、ラッスス(ラッソとも呼ばれている)、パレストリーナの没後400年を記念し、昨年から行われている演奏会である。音楽監督は菅野浩和氏、合唱団は椙山(すぎやま)女学園大学合唱団、同校のOGで構成されているアヴェス・ユヴェネス、中央大学音楽研究会グリーンクラブ、いずれも菅野さんが育ててこられた総勢約100名の合唱団である。
まず、巡礼歌を歌いなが会衆席の後方から合唱団が入場する。コンサートは菅野さんの簡単な解説を交えて、モテット、ミサなどのカトリックの典礼の曲がグレゴリオ聖歌を交えながら進行し、合唱団の退場で静かに終わった。わが国では宗教曲といえば、プロテスタント派であったバッハの作品が中心であるが、菅野さんは、それより約一世紀前、ルネッサンス時代のカトリックの典礼の音楽が現在の西洋音楽の原点にあるとして、その音楽の掘り起こしに熱意を捧げられておられる。
まだ、音楽がひたすら神の栄光の賛美にささげられた時代の頌歌である。素朴で清澄な旋律、ゆったりと織り合いながら進行する声のアンサンブルが聖堂に流れ、敬虔な感動を呼び起こした。至福としかいいようのない一時であった。
サントリーミュージアム[天保山]のオープン
11月3日、大阪のウォーターフロントである天保山の一角にサントリーミュージアムがオープンした。この地区には海遊館として知られている大型の水族館があり、足の便もよく新しい行楽地として賑わっている。
このミュージアムは球形のIMAXシアターを中心に、二層の展示ギャラリー、レストラン、スカイラウンジ、ミュージアムショップなどで構成されたユニークな外観の建物である。建築設計は安藤忠雄氏である。
IMAXシアターとはImage Maximum とのこと、カナダで開発された大型の3D(三次元)立体映像システムである。上映された映像はこのシアターのために制作された『ブルーオアシス』という海の生物の生態映画。高さ20m、幅28m の大型スクリーンに写し出される映像は従来の映画からは想像できない迫力であった。
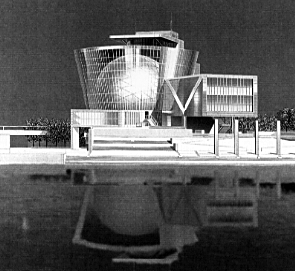
展示ギャラリーでは、東京のサントリー美術館の収蔵品である美人画を中心としたポスター展示が行われていた。有名なロートレックの作品から、昔、酒屋の店頭を飾っていた赤玉ポートワインのポスターなど懐かしいポスターがあった。
また海辺のイタリアンレストランはメニューも多く、自家製のパンも美味しかった。ミュージアムショップにはガレ風のガラス製品からリトグラフ、文房具など洒落たグッズがならんでいた。この施設は東のサントリーホールに対応したサントリー社の文化活動の西の拠点である。昼だけではなく、夜も楽しめるのがよい。JR梅田駅まえから市営バスの便もある。いずれ、海辺に水上ステージが設けられることを聞いた。夏の夜のイベントが楽しみである。
盛況だった輸入オーディオショー
低迷が続くオーディオ界をよそに、輸入オーディオショーが今年9月22、23日の二日間、東京九段のホテルグランド・パレスで開催された。欧米の100を越えるオーディオ各社の製品が17の代理店によって展示された。もちろん、製品はハイ・エンド指向の高級品が中心であったが、今年とくに目だったのは真空管アンプであり、その外にも、レコードプレヤー、カートリッジなどアナログ製品、オーディオケーブルなどの展示が目についた。
各社のブースでは、オーディオ評論家の方々のスピーチを交えた試聴会にファンが溢れており、かつてのオーディオ・フェアの熱気を思い出した。わが国のオーディオ界との大きな違いはトーレンス、オルトフォン、マッキントッシュ、タンノイなどカメラでいえば、ライカ、コンタックス級の老舗ががんばっている点ではないかと思う。会期はたったの二日間、ホテルの2フロアーのショーであったが、ここにはオーディオの魅力が凝縮しているように思えた。
第43回オーディオ・フェアの印象
今年のオーディオ・フェアは10月13日から17日の5日、池袋サンシャインシティ・コンベンションセンターTOKYO にて開催された。今年のテーマは“夢、感動、原点”であったが、予想のとおりオーディオの原点を感じさせる展示は隅に押しやられた感じで、目についたのは今はやりのナビゲーターなどの製品で、エレクトロニックスショーの家電版といった感じで、ディジタル、マルチメディアに発散している最近のオーディオ界の姿勢そのものを象徴しているショーであった。12月6日を“音の日”として、オーディオの原点への関心を呼び起こそうとしているあの協会の勢いはどうなったのであろう。アメリカ大使館から借用してきたというエディソンの最初の蓄音機のレプリカは会場の端のガラスのケースの中に収まったまま、何の説明もなかった。足をとめた人はどれだけいたのであろうか。
道具や手法だけがやたらに発達して、その先に掲げるべき音の原点への関心がうすれてしまっているのが現在のオーディオ界である。残念である。今年の入場者の数は5 日間で133,060名、昨年と比べて微増という点が事務局の発表であるが、このような数だけでしか評価できなかったのが今年のオーディオ・フェアであった。(永田 穂 記)