古楽器演奏と日本のコンサートホール
「古楽器」あるいは「オリジナル楽器による演奏」と銘打ったCDを見ることも最近では珍しいことではなくなった。大きなCDショップに立ち寄れば、バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンといった作曲家の作品はもとより、今や初期ロマン派のレパートリーまで「オリジナル楽器」による演奏で再現されている。こうした古楽器運動も最近定着し、一時期のようにCDなどの「複製メディア」を通じてだけでなく、コンサートホールにおいても生で演奏を楽しめる機会が増えてきた。ここ2 ~ 3年、東京で行われた古楽器による演奏会を思い出してみても、トン・コープマン、ガーディナー、ブリュッヘン、クイケン、ホグウッドといった指揮者たちが自らのオーケストラを率いて来日したほか、室内楽やフォルテピアノのコンサート、ひいてはバロック時代のオペラまで古楽器によるオーケストラで上演[1992年ルネ・ヤーコプスによるモンテヴェルディ《ユリシーズの帰郷》]という贅沢な機会にもめぐまれた。また外国からのアーチストのみならず、国内においても鈴木雅明氏や有田正広氏などが、積極的に古楽器による演奏活動を続けている。地理的空間はもとより歴史的時間を越えて、ソフトとハードを通じてさまざまな音楽を耳にできる環境に我々は生きているということができる。
しかし一流の古楽奏者たちによる演奏をこうして楽しむようになって、誰もがふと疑問を抱き始めた。それは、こうした古楽器演奏と現代のコンサートホールとの「演奏の場のズレ」である。せっかく小編成で組まれたオーケストラや合唱も、繊細な古楽の音を聴くには、演奏される場が大きすぎるという意見である。最近では都内にも 500席程度の小ホールや1,000 席以下の中ホールが次々と誕生し、利用する側もホールをうまく使い分けるようにはなった。それでも、「もう少し小さな空間で聴けたら・・・」という声を時折、新聞・雑誌の音楽批評欄などで見かける。演奏家のスケジュール、また主催者や招聘元の経営的な問題もあるわけで、無論単にホールの容量だけでその演奏会の場を決めることはできないだろう。しかしこのような古楽ブームによって、我々が音楽史上の傑作ばかりでなく、新たな音楽の世界に目を開かれたことは事実である。そしてこの「開眼」は、これまでいわゆるクラシック音楽そのもの、またその演奏の側面ばかりに捉われていた我々に、それらが「どんな空間で演奏されていたのか」という意識を初めてもたらしてくれたように思う。すなわち先に述べた疑問が、この意識をもたらす引き金ともなったのである。
古楽への関心が広まった背景には、音楽学や楽器学において、ヨーロッパ音楽の演奏実践、演奏スタイルについての研究が進んだこと、そしてその研究成果を活かした演奏を忠実に録音・再生できる「複製メディア」の技術的な進歩が大きく関わっていることも事実である。微妙な音色のニュアンスを身近な再生装置で聴けるようになったことは、確実に古楽のファンを増やす要因となったのである。こうして人気を得た演奏家が来日を果たし、期待に胸をふくらませてコンサートに行ったものの、そこで人々の頭をよぎったのは「演奏会場がもう少し小さかったら?」ということだった。ヘッドホンや優れた再生装置で得たほどの精密な音の体験に比べ、コンサートホールではいまひとつ満足感を得られないと感じる人もいた。結局、現代の日本でヨーロッパの古楽が演奏されたアクチュアルな場を再現することは、ほとんど不可能なことなのかもしれない。いや、われわれ異文化を持つ日本人がそこまで再現する必然性もないという意見もあるであろう。むしろ大事なのは、この「意識のズレ」から、ヨーロッパ・クラシック音楽のアクチュアルな姿を捉えつつ、現在の日本のホールの在り方、音楽との接し方を見直すことではないだろうか。
これらはすぐに答えを見出だせる問題ではないが、まず、例えば古典派音楽がどのような場で演奏されていたのか、そのような切り口から考えてみたい。
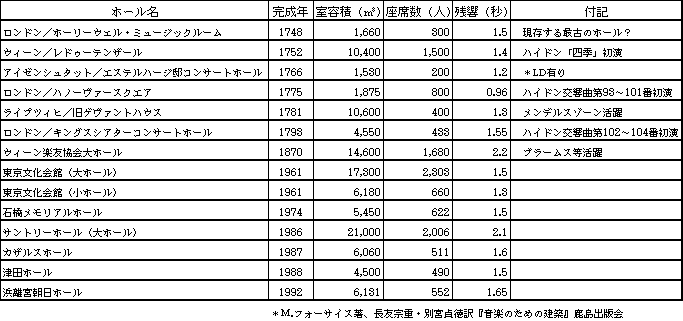
上記の表は、実際の演奏記録の残っている18世紀の音楽空間と、現在の東京にある主なホールとの室容積、座席数を比較したものである。例えばロンドンのハノーヴァー・スクエアは、J.ハイドンがP.ザロモンに連れられ、1791年から94年にかけてロンドンの聴衆のために交響曲第93~ 101番を作曲、自ら演奏した場所である。さらに1793年には、このハノーヴァー・スクエアより一回り大きなコンサート会場、キングス・シアター・ホールがオープンした。このためにハイドンは引き続き第102番から104番までの交響曲を作っているが、残響時間も長く、室容積も大きくなったこの場所を意識してか、彼は先の作品群よりも大きな編成を使ってシンフォニーを書き上げている。フォーサイスによれば、前者のハノーヴァー・スクエアは中音域の残響時間が1 秒に足らず、かなりドライな音響だったという。これに対し後者のキングス・シアターは、残響時間も長くなっている。音響学者のJ.マイヤーは、ハイドンがこうした音響効果を考慮に入れ、個々の楽器に強弱記号をつけつつ曲を作っていたとの見解を示している(マイヤー、1978年)。
同時期のウィーンの音楽空間についての資料は、今回まだそろえられなかったが、ここにあげたレドゥーテンザールに引き続き、ウィーンのコンサート会場として使用され、例えば1808年、ベートーヴェンの交響曲第5 番・6 番が初演されたというテアター・アン・デァ・ウィーンが、これらと比較してどのような空間だったのか興味あるところである。フォーサイスは、明晰さを根底に持つ18世紀の音楽のディテール(基本旋律を彩る装飾や音のつやなど)、ほのかな感情のうつろいなどは、「当時の小じんまりとした、聴衆のあふれがちな会場でこそ冴えざえと浮かびあがる」とし、それに相応しい空間としてロンドンのホーリーウェルやハノーヴァー・スクエア、旧ゲヴァントハウスなどをあげている。また容量は大きくなり、残響は多くとも、幅が狭く、側方反射音が豊かなウィーン楽友協会の大ホールは依然として古典派音楽に適しているという。しかしこの楽友協会の場合、残響の豊かさはまたロマン派の音楽にも適した空間だという。アムステルダムのコンセルトヘボウにしても、「残響で音が交じり合う効果は、いってみれば印象派の絵画の筆さばきで、題材がぼやけるために見る人はいきおいそのイメージをとらえようとして自分の感覚、情動を作品に投射することになる」(フォーサイス)。こう考えてみると古典派の音楽とロマン派の音楽とでは、ほとんど対照的といっていいほどの音楽空間が必要なのかもしれない。表にあげた古典派音楽向きの空間と現在の主な小ホールと比較してみると、これらがいかに小さな空間だったかが想像できる。古典派の音楽ばかりでなく、それ以前のバロック、ルネサンスの音楽を古楽器で聴く機会も増えている今日、どちらかといえば、大編成オーケストラ向けの現在の日本の大ホールで古典派の音楽を演奏したとき、ある種の「物足りなさ」を感じるのは当たり前のことなのかもしれない。
一年ほど前にフォルテピアノを勉強しているという演奏家の方に、その魅力を尋ねたところ、その人は古典派音楽の魅力を小さいダイヤモンドに譬えていた。「それは小さい中に輝きがあるからこそ、そばで接して美しさを感じるのであって、大きく引き伸ばされ、遠くで眺めても何の魅力もない・・・」と。この言葉を聞いた時、私は学生時代、とある邦楽の先生の授業で三味線を聞いた後、「こういう音楽は小さな畳の部屋で、好きな女の子とでも聴くのが一番いいのよ」と言われた時のことを思い出した。そういえば、ごく小さな空間で、身近に生で音楽(音)に接するという機会が何と少なくなってしまったことか..。いやこういう場がほとんどなくなってしまったことが、現在の日本の音楽文化の現状なのかもしれない。(永田 美穂 記)
八ヶ岳高原音楽堂コンサート
春のコンサートシーズンになると、会場の入口でもらうチラシの中に八ヶ岳音楽祭の豪華な案内が目につく。武満徹氏、リヒテル氏などを音楽監督として、世界のトップアーティストによって繰り広げられるこの音楽際は、期間は短いがその内容は充実している。ただし、その入場料と宿泊料金にちょっとためらってしまうというのが一般の音楽ファンではないだろうか。ちなみに、今年のコンサートのチケットは13,000円、ディナーパーティ付きで25,000円という値段である。同じ設計者のしかもスタイルまで同じ音楽堂で高原音楽祭を続けている草津とはこの点からみても、狙いも雰囲気も違う音楽祭であることが想像できる。(注:草津は音楽アカデミーが中心のフェスティバルである)それだけに、一度足を運んでみたいと思っていたが、8 月5 日、夏の夜のサロンコンサートとして、吉原すみれさんのパーカッションリサイタルを聴く機会を得た。
この八ヶ岳音楽堂はJR小海線野辺山駅から車で約15分、海の口牧場の奥に位置する別荘地の中、落葉松や白樺の林に囲まれた一角にある。国道141号線から案内にしたがって側道にはいると、始めての訪問者には心細くなるような畑の道が続く。しかし、別荘地区になると道路も整備され、この施設の中心である八ヶ岳高原ロッジに着く。車で来た客もここで駐車場に車をおいて送迎バスで会場に向かうというシステムである。ここから音楽堂まではさらに車で5 分以上かかる。音楽堂の駐車場は狭く、しかも距離が離れている。風景や建物の姿は似ていても、このようなアプローチの仕方一つにも草津とはまるで違っている。
音楽堂は吉村順三氏の設計、音響はヤマハの川上氏のグループである。ホールは八角形の平土間で、ステージ、客席が自由に構成できる、“アダプタブルステージ”である。客席数は最大で250席とのこと。一枚の大屋根が客席空間を覆っており、その中央部は突出したガラス屋根である。外壁はコンクリートの打放し、ホール周辺は全面ガラスで、周囲の緑や星空がそのまま目に入る。落葉松の林の中の木のホールという印象である。このあたりの調和は草津より無理がない。音響処理も目につくのは天井のスリットくらい、残響可変パネルが壁の所々に設けられているとのことであったが、当日は使用されていなかった。

ホールの規模に比べてホワイエは広く、コンサート前と休憩時にはワイン、コーヒー、ジュース、日本茶などのフリーサービスがある。すべてがハイソサエティ嗜好といったらよいであろうか。
コンサートの開始は6 時、まだ、空に明るさが残っている夕刻のコンサートである。場内は真っ暗、吉原さんのパフォーマンスがシルエットで浮かぶが、平土間だけに全貌がみえない。それに、窓面が大きいから明暗のコントラストが強すぎてやや疲れる。後半になってやっと照明が入った。
室内はほぼ満席、パーカッションに対しての響は心地よかった。大音量にも余裕があり、しかも色とりどりの打楽器のアタックの音が鮮やかに耳に入ってくる。多分、ピアノにもよいであろう。しかし弦の音はどうであろうか。このような小容積のホールでは大ホールと違って、響きに包まれた音楽を楽しむというより、むしろ、一つ一つの音の構成のディテールから音楽や音の面白さが味わえるのではないだろうか。民族音楽や現代音楽など機会があれば、このような空間で聴いてみたいと思った。
草津とおなじように、この音楽堂も冷房はないように見受けられた。草津で経験したことだが、高原といえども夕方には冷気が流れ、閉じられた室内は案外湿度が高くなる。しかし、空調音のない絶対的な静けさは、戸外で感じたあの真の闇とともに、貴重な体験であった。94年度の音楽祭は9 月の22日から25日まで、今年のテーマは「祈りと音楽」。7 つのコンサートが行われる。問合わせは、音楽祭予約センター(Tel:0120-213217)まで(永田 穂 記)