アート・スフィアの誕生
最近、浜松町から羽田空港までのモノレールの所要時間が18分と、従来より2分ほど余計に掛かるようになったのをご存じだろうか。浜松町駅と大井競馬場前駅の間に天王州アイルという新駅がこの6月19日に誕生したためである。この新駅は、高層ビルが数本立ち並んだ再開発プロジェクト“シーフォート・スクェア”のオープンに伴って開設されたものである。以前は倉庫が並んでいたこのお台場地区を三菱商事、第一ホテルエンタープライズ、宇部興産開発らが開発を進めてきたもので、約22,000m2の区画にオフィス、ホテル、住宅、劇場、商業・サービス施設等の都市機能が配備されている。
“アート・スフィア”というのは、この新都市の中に文化の象徴として設置された劇場で、馬蹄形3層構造の客席に746席を擁している。主な特徴として、コンピュータ制御による点吊りシステムを導入した舞台名物、切り穴を任意の位置に設定できる可動舞台床ユニット、客席天井部にも大型スピーカを配した音響システム等の舞台設備があげられる。しかしながら、この劇場の一番のアピール・ポイントは何といっても舞台と客席の距離が最大でも20mで、どの客席からも舞台が近くて見やすいということ、ダイナミックで臨場感あふれる客席構成と木質系を主体とした落ち着いた材質感が上手くデザインされていて魅力的な空間が現出されているということであろう。“雰囲気のある”劇場の誕生である。
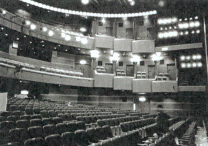
ハードが完成した今、来る10月5日のオープニングに向けての準備が着々と進められている。この劇場の企画、運営は三菱商事出資によるスフィア・コーポレーションが担当し、ここで行われる年間約100日間の自主企画公演を様々な分野の企業で構成されるグループ“東京オピニオンズ”が主催する。まずオープニング・シリーズとして、92年10月から93年3月までの約6か月間に以下の8演目、100余公演が予定されている。
- オープニング・コンサート“ナタリー・コールwithフルオーケストラ”(‘92.10/5~9)
- チェンジング イメージ オブ ザ オペラ“浜辺のアインシュタイン”(‘92.10/18~25)
- ストレートプレイ“カフカ/変身”(‘92.11/10~29)
- ミュージックショー“朊部家の人々”(‘92.12/4~8)
- ポップス“X’masコンサート”(‘92.12月上旬)
- ダンス“ニューイヤー・エトワール”(‘93.1月上旬)
- オペラ“中丸三千繪のオペラ「声」”(‘93.1月下旬)
- オリジナル・ミュージカル“ホンコン・ラプソディー”(‘93.3月~4月)
一部のチケットはすでに売り出されているものもあり、特定の演目、公演日をご希望の場合は早めのお買い求めがよいかもしれない。(チケット予約、購入:アート・スフィア・チケットセンターTEL.03-5460-9999/問合わせ:アート・スフィアTEL.03-5460-8511)(豊田泰久 記)
ヨーロッパのホール研修ツアー報告(第2陣詳報1)
今月より2回にわたり、第2陣の研修ツアーで訪れたホールの概要、コンサートの印象などについて報告したい。
バーミンガムでのシンポジゥムとシンフォニーホール
5月18日、19日に開催されたシンポジゥム“Acoustics,Architecture & Auditorium”では、物理音響・聴覚心理に関する学術レベルの研究からホール・オペラハウスの建築史、ホール設計例の紹介などホール音響に関する幅広い話題が提供された。第一日目の夜には会場に隣接するSymphony Hallでのコンサート観賞が企画され、それに先立って同ホールの音響コンサルタントJohnson氏、建築家Graham氏の講演があった。Johnson氏と氏の主宰するArtecスタッフの講演では、このホールの室内音響的な特徴であるステージ上の大型可動キャノピーと、ホール周辺にエコールームを導入するに至った経緯の説明があった。初期反射音を得るための浮き雲反射板やステージ反射板の隙間を介しての裏側空間との音のエネルギーのやりとり(カップルドルーム)が彼独自の設計コンセプトである。講演後の質疑では、このホールの残響時間が問題となり、カップルドルームでは途中で折れ曲がった減衰波形が観測されるため、残響時間そのものの概念があてはまらないとするArtecスタッフと、残響時間を重視する参加者との間で、時間をオーバーしてのやりとりがあった。最後には、この夜のコンサートを聞いて残響時間のアンケートをとる提案まで飛び出した。建築家Graham氏の講演では、Johnson氏の提示したホール形状を建築的にまとめ上げていく過程が紹介された。音響コンサルタント(実際にはJohnson氏は劇場コンサルタントも兼ねているが)が先に決まり、その基本プランに沿って設計が進められるというプロセスは非常に特殊であり、少なくともわが国では馴染みにくいのではないかと思う。このホールと双子的な存在のダラス・シンフォニーホールも同様な設計プロセスであったと聞く。
さてこの夜のコンサートは、ロシアのノボシビルスク・フィルによるショスタコーヴィチの交響曲第5番をメインとするオールロシアン・プログラムであった。私はこのホールはもとより、このオーケストラを聞くのも初めてではあったが、ホールは一言でいって“よくできた(考えられた)ホール”という印象であり、ロシアのオーケストラ特有の強大なパワーをも包み込んでしまう余裕があり、なおかつ弦楽の弱奏、tutti部分でも素直に“鳴って”いた。たまたま、このあとのウィーンでもフィラデルフィア管弦楽団で同じショスタコーヴィチの5番を聞くことができたが、バーミンガムの方が多様な演奏者、曲目に対応できる“間口の広さ”を兼ね備えているように感じられた。
このコンサートでは、ステージ上のキャノピーは15m程度の高さにセットされており、エコールームの扉は閉じられていた。この処置は、2週間程前にJohnson氏が決めたそうである。約半年前、双子のダラス・シンフォニーホールでこの扉が1/3程度開いている状態でのコンサートを聞く機会に恵まれ、GP(総休止)や楽章の終りでの異様に長い響きの残り方に驚いた記憶がある。楽曲途中でのエコールームの効果についてはいまだに把握できていないが、今回のコンサートを聞く限り、あえて響きに尾鰭をつける必要はないのでは、というのが実感である。ところで、前述の残響時間のアンケート集計結果では、平均値1.7秒のまわりで1.4秒~2.6秒の範囲にバラついていた。(小口恵司 記)
ベルリン・フィルハーモーホールとベルリン・フィル
このホールでのプログラムは、バーンスタイン作曲のピアノとオーケストラのための交響曲第2番(ピアノソロ/ジェフリー・シーゲル)とドヴォルザーク作曲の交響曲第7番で、オーケストラはもちろんベルリン・フィル、指揮はレナード・スラトキンであった。
興味は何といっても内装天井が張り替えられた後のホールの音響のことである。この大ホールがオープンしたのは1963年のことであるが、それから25年経った1988年の6月、ステージ上部の天井の一部が突然剥がれ落ちるという事故があった。幸い人身事故にはならなかったものの、それ以上の落下防止のためにホール全体にネットが張られた状態でその後のコンサートが続けられた。1991年1月から全面的にホールを閉鎖した上で内装天井の全面的な張り替え工事が実施され、つい先日1992年の4月26日のコンサートをもって再開されたのである。この間のコンサートは、隣接している室内楽ホール(約1000席)と旧東ベルリンのシャウシュピールハウスでもって代用された。筆者が昨年9月に訪れたときはまさに改装工事の真最中であり、ホール内全体が工事用足場で埋まっていた。改装にあたっては、もとの天井そのままを再現して意匠的にも音響的にもできるだけ変えないことに注意が払われた。ホールスタッフから説明を受けた範囲では、強度の関係から天井材の厚みがやや増えた(石膏約20mmから25~30mmに)とのことである。
コンサートの日は(5月20日)ホールが再開しておよそ1か月経っていたが、前報のとおり一見してホールが新しいという印象は全くといってよいほど無かった。せいぜいていねいに掃除されたといった程度のものである。コンサートを聴いた席は、前半はオーケストラ背後の最前部、後半は正面中央部(いわゆるど真ん中あたり)であった。前半はステージのすぐ近くということもあって、このオーケストラの並外れた能力を楽しめた。柔らかくてしかも芯のある太い音、十分な音量感でしかも音が沸き上がってくるような印象は他のオーケストラではなかなか味わえない。
後半の正面中央部で聴いた限りではホールの音響が以前に比べてさほど変わったような印象は受けなかった。すなわち、バランスよく素直なものの基本的に鳴りにくいホールであり、オーケストラの強大な音量がそれを補ってトータルとして非常に優れたものとなっているということである。ダイナミックな客席配置によるホール空間の素晴らしさは他に比べようもなく、依然として偉大なホールであることは間違いないが、このホールはベルリン・フィルというオーケストラと一体となって始めてその真価を発揮する。他のオーケストラ、特に音量の小さめのオーケストラではちょっと鳴らし切れないであろう。
当日、特に正面中央席では低弦がやや弱めであることが気になった。もっともこれは一夜のコンサート、しかも限られた席での印象であるので、天井の改装が影響しているのかどうかは定かでない。指揮者、曲目、オーケストラの編成、コンディション等々、影響しそうな要因はいくらもあるし、オーケストラ自身のバランスが以前と変わってきているということも十分考えられる。
カラヤン全盛期の頃に比べて晩年はカラヤン自身によるトレーニングの時間が減ったことで、オーケストラのアンサンブルのレベルが低下したことがしばらく心配されていた。昨年9月のコンサートは新音楽監督アバドの指揮でシャウシュピールハウスで行われたが、この時はアンサンブルの中に不純物がわずかながら残っていて時折それが顔をのぞかせていたのを覚えている(この時はそれよりも、シャウシュピールハウスという歴史的なシューボックスホールに近い形状、大きさのホールでは、やはりベルリン・フィルの音は強大すぎてうるさいという印象が強く残った)。今年1992年の2月に同じくアバドとともに来日した時、驚いたことにアンサンブルはほとんど完璧なまでに元のレベルに戻っていたが、さらに驚いたのはオーケストラの質、バランスが以前とは少し変わっていたことである。特に低音域において、以前のカラヤン時代の重厚強大なイメージがもう少し軽くて颯爽としたものとなっていた。曲目はすべてブラームスの作品であったが、テンポも早めだったこともあってまさにイタリア風のブラームスという印象を持った。指揮者のアバドがイタリア人であるという先入観からだけのものではあるまい。
カラヤンが亡くなり、ベルリン・フィルの音楽監督、常任指揮者が代わり、ベルリンの壁が無くなった。そしてフィルハーモニーホールの天井までが剥げ落ち一新された。ベルリンではあらゆる物が変わりつつある。あまりに同時期で象徴的な気がしてならない。(豊田泰久 記)
NEWSアラカルト
カザルスホール、墨田区文化会館のオルガンビルダー決まる
計画当初からオルガン設置が予定されていたカザルスホール、墨田区文化会館のオルガンのビルダーが決まり、本年度中に発注される運びとなった。カザルスホールは旧西ドイツのアーレント社、墨田区文化会館は旧東ドイツのイェームリッヒ社である。オルガンの詳細は後日述べるとして、ビルダー選定までの経緯があまりにも対称的なので紹介したい。
墨田区の場合は公共施設であるだけに、オルガン委員会による審議という方式をとった。委員として丹羽正明、広野嗣雄、馬淵久夫氏というオルガン専門家のほかに、墨田区の音楽専門委員の森千二氏、新日本フィルの松原千代繁氏というホールの運用、使用者が加わったこと、審議の途中で2名の委員によって欧米のビルダー3社の訪問、審査まで行ったことがこれまでの委員会にはない特色であった。結局、オーケストラとの音色の調和という点でイェームリッヒ社が選ばれた。
これに対して、カザルスホールの場合はまったく異例ともいえる決まり方である。カザルスホールの総支配人で主婦の友社社長の石川康彦氏、ヴィオラの今井信子さんのお二人が東京郊外の聖グレゴリアの家を訪れ、そこでこのアーレントオルガンと出会い、その音色に魅了され、たちどころに決まったという経緯である。石川さんの言葉をかりるならば、長年求めていた音に出会った、という感動的な一瞬だったという。
アーレント社のオルガンは17世紀前後の北ドイツバロック様式の建造法によるヒストリカルなオルガンであり、イェームリッヒ社のオルガンは名器ジルバーマンの音色を継承しているコンサートオルガンであると聞いている。完成はカザルスホールが1998年、墨田区が1996年とのこと、関係者にとっては待ちどおしいオルガンである。