バーミンガムの新しいコンサートホール
イギリスのバーミンガムに今年の4月にオープンしたばかりの新しいコンサートホール(バーミンガム・シンフォニーホール、2200席)を訪問する機会を得た。バーミンガムはロンドンから北西方向に電車で1時間40分程にあるイギリス第2の都市である。もともと重工業を中心に発展してきた工業都市で、観光ガイドブックなどにもほとんど取上げられていないが、クラシック音楽界ではサイモン・ラトル率いるバーミンガム市交響楽団(CBSO)の吊とともにここ数年の間に急にその名前が広まってきた感がある。今年2月、CBSOがラトルとともに来日した時に知己を得ていた関係で、新しいコンサートホールのディレクターであるJowett氏を訪ねることができた。ホール建設のいきさつなどの話を伺いながら、ちょうどその時来演していたクルト・マズア指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のリハーサルと本番を聞くことができた。
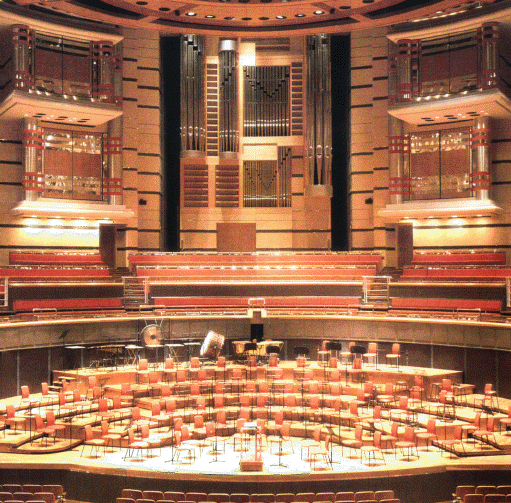
コンサートホール建設の計画自体は古く、17~18年程も前からバーミンガム市がCBSOに対して専用のコンサートホールを作ることを約束してきたが、1979年サイモン・ラトルがCBSOの首席指揮者に招かれてからオーケストラのレベルが急速に高くなり、ラトルの市当局に対する熱心な説得とともにホール建設の機運が熟してきたとのこと。折りしもバーミンガム市では重工業中心の経済、そして市全体の斜陽化の中で、市としてのアイデンティティを文化に求めようという政策の一環で大規模なコンベンション施設(International Convention Centre)の建設が1983年から計画され、シンフォニーホールはコンサート専用のホールとしてその中に設置された。
International Convention Centreにはコンサートホールの他に大小合わせて10の会議用や展示用のホールがあり、その他にレストランや売店等が併設されている。センターの周辺一帯は文化施設のゾーンとして計画されており、レパートリー・シアターが隣にあるほか、センターに隣接して建設されたホテル(ハイアット)とセンターとは2階レベルの歩道橋で直接結ばれている。
ホールの基本的な形状は、天井が高く横幅の狭いいわゆるシューボックス型と呼ばれているものに近いが、平面形状は厳密には矩形ではなく両端が半円形の「小判型」形状となっている。客席後部と両側面に3層のバルコニー、ステージ背後にはコーラス席兼用の客席が設けられているが、客席後部のバルコニーのうち最上部はかなり奥深く、2200席を確保するための工夫、苦労の後がみられる。建築設計はPercy Thomas Partnership、音響設計はニューヨークのコンサルタントのRussell Johnson氏(Artec Consultants Inc.)である。ジョンソン氏は2~3年前にオープンしたダラスのコンサートホールの音響設計も担当しており、このダラスとバーミンガムの2つのホールはその規模や音響の考え方の点で非常によく似ており双子のようなものである。Jowett氏によればバーミンガムのホールはダラスのものよりやや大きく、あらゆるものが大きいダラスと比べて唯一大きいものがこのホールだそうである。
内装は木を主体に使った暖かい感じで、所々に散りばめられたメタル装飾が同時に豪華で華麗な雰囲気を醸し出すのに役立っている。
音響面での大きな特徴は次の2点である。
- ステージ上部に大型の可動キャノピーが反射板として吊られていること
- 建築音響的に残響を付加するために大容積のエコールームがホールの躯体周辺に設けられていること
(1)のステージ上部の反射板は大型の一体形状で客席中央部あたりまで舌状に張り出しており、ステージ照明設備等も組み込まれている。保守点検もやり易いようにステージレベルまで下ろすことができ、その間の任意の高さにセットできるようになっている。
(2)のエコールームは主としてステージ側背後に大きなコンクリート箱として設けられ、ホール内部数箇所に設置された開口部の扉の開閉を調節することによってエコールームからホール内へ放射される残響の量を調整、ないしは可変しようという仕組みである。どちらの設備もダラスとバーミンガムの両方に導入されているが、特に後者はジョンソン氏独特の考え方によるもので、ホール形状の工夫と残響音の調整によって明瞭度と残響感をコントロールしようという意図である。一足先にオープンしたダラスのホールにおける残響調整装置に対する評価は賛否両論で、効果的であるという人と疑問視する人とに評価が分かれている。私は残念ながらダラスのホールは未だ体験したことがない。
さて、バーミンガムの音響についてであるが、個人的には大変好印象を持った。曲目はベートーベンのヴァイオリン協奏曲と交響曲第1番で、ホールの音響を判断するには一般的で好都合なプログラムである。ただ一度のリハーサルとコンサートしか聞いていないので断定的なことはいえないが、各楽器間のバランス、高音・低音のバランスが非常に良く、ホール空間も素直に響いている印象であった。決してホール全体が鳴り響いているという印象ではなかったが、その分ロマン派あるいは近代のもっと大きな編成の曲目に対しては余裕を持って対応できるかもしれない。
ジョンソン氏の残響調整装置の扉は、ほぼ半開の状態であった。その場で開閉して聞くことができたわけではないので、その効果、良い音響に対する寄与の程度については残念ながら分からない。ステージ上の可動反射板の高さについては、当日はステージ床から16m程度に設定されていたとのことである。
リハーサル後の指揮者マズア氏のコメントは「ライプツィヒ・ゲヴァントハウスのホールとバーミンガムのホールとは基本的な室形状が全く異なっているのに、ステージ上での音響的な印象は大変よく似ている」。いずれにしても音響的には好印象のようであった。
コンサートの休憩時間に会ったバーミンガムの指揮者ラトル氏のコメントは「自分は4月のホールオープン以来、未だ2回しかこのホールで演奏したことがない。しかし、そのいずれの時よりも今夜のコンサートの方が音響が素晴らしい。ジョンソン氏はその後いろいろと音響の調整をしたに違いない」。わざわざニューヨークから来訪していたジョンソン氏(彼はリハーサルの間もずっとホールのあちこちで聞き歩いていた)にラトル氏のコメントについて聞いてみたところ「ラトルが演奏した時と比べて変わっているのはステージ上の可動反射板の高さだけで、前の時より約3m高くして現在約16mになっている。その他は何もさわっていないよ。」と、笑いながら語ってくれた。
今、わが国ではコンサートホールの建設がひとつのブームといえるほどで、欧米へのホール視察も盛んに行なわれていると聞いている。このバーミンガムの新しいホールは、ウィーン、ベルリン、アムステルダムといった従来の名ホール訪問旅行に是非加えていただきたいホールである。(豊田泰久 記)
バロックザール(青山音楽記念館)
京都のバロックザールからは毎月催物の案内をいただいており、また、音響仲間の伊東東平さんの設計という事もあって、ぜひ一度訪ねたいと思っていた。また、このホールの音響については、同志社の音楽科の学生の“私の好きなホール”についてのリポートの中にもうがった内容の記事があり、ここでの演奏会を楽しみにしていた。念願がかなって、9月24日、”September Concert”という歌とピアノの夕べを聴くことができた。
このホールは京都の西、阪急嵐山線の上桂駅から歩いて5分、四条河原町から30分もあれば十分という位置にある。200席の小ホールとは聞いていたが、ロビーから入ったところが最後列、後ろにもう少し客席が欲しくなる。しかし、ステージをみている限り天井も高く、中ホールを思わせるコンサート空間である。音響的な仕掛けとしては、壁が僅か内側に傾斜していることと、残響調整用のカーテンが慎ましくおさめられているくらいで、ごたごたした細工がないのが心地よかった。気になったのは天井の換気口である。
私は上手の最後列に近い席をとった。歌とピアノという、どちらかといえば明瞭さが求められるプログラムであったが、関心したのはその響きとクリアーさのバランスの良さであった。音の輪郭も明確であり、しかも刺激的でなく、低音域から高音域にかけてのバランスのとれた明るい響きであった。
最近、各地に小ホールが誕生しているが、小ホールでは大ホールで苦心する初期反射音の確保の問題はない。しかし、客席の大部分が音源に近い領域に位置するという別の課題がある。また、楽器の種類も編成の規模も、したがって、音量や音色の範囲も広く、響きの設計の焦点をどこにおくべきかは大きな課題である。最近では古楽器から邦楽まで登場してきた。小ホールの音響設計では大ホールとは違ったアプローチが必要なのである。
小ホールの設計ではとくに音場の拡散が気になってくるが、拡散と音響効果との関係は実のところ明らかではない。このバロックザールの拡散対策は5°という僅かな壁の傾斜と天井のゆるやかな曲面くらいでしかない。しかし、刺激的な響きはまったくなかった。私の席が最後部に近い位置であったこと、また、今回は弦楽器の音を確認できなかったことなど、一回のコンサートで断定はできないとしても、このホールの響きのバランスは見事である。それに演奏もこのホールの響きを心得たものであったように思う。
後日談になるが、ほぼ、同じ時期にこのホールで行われたワイセンベルグのピアノリサイタルの印象をあるプロジエクト仲間から聞いたが、わんわんでディテールがまったく分からなかったとのこと、当然だと思う。実はサントリーホールでもザ・シンフォニーホールでも今回のこの巨匠の演奏は同じ印象であったから、あの弾き方ではこのホールには合わないことは確実である。音量に対して許容の間口が狭いことは響きの豊かな小ホールの宿命であり、この点は演奏者に考慮して頂きたい事項である。ともかく、この小ホールはいろいろな点を示唆してくれるホールであった。
NEWSアラカルト
東京芸術劇場ガルニエオルガンの披露コンサート
本紙でも何度か紹介した東京芸術劇場大ホールのガルニエオルガンが完成、22日に披露演奏会が行われた。予定から約1年おくれての完成であり、いろいろな意味で話題を呼んだオルガンである。このオルガンは17世紀初頭のオランダ・ルネッサンスタイプ、18世紀の中部ドイツ・バロックタイプ、フランスの古典、およびシンフォニックタイプという、調律法もピッチも異なる4種類のオルガンを3台の回転台の上に集合させた世界でも初めての126ストップのコンサートオルガンである。当日は、ガルニエ氏のオルガンの解説に引き続いて、それぞれの音色を生かした演奏が、椊田義子、鈴木雅明、早島万紀子、廣野嗣雄の4人のオルガニストによって行われた。今後のコンサートオルガンの方向を示唆するオルガンとして、その運用が楽しみである。

オルガン研究会からのお知らせ シンポジゥム“日本のオルガンはこれでよいのか”(2回目)
10月26日、15~18時、六本木の鳥居坂教会において、東京芸術大学助教授広野嗣雄氏の司会で標記のシンポジゥムが開催される。パネラーはオルガン製作者を代表して望月広幸氏、須藤宏氏、評論家の丹羽正明氏、オルガニストの保田紀子氏の4氏である。この教会には、ガルニエ製作のオルガンがあり、新山恵理氏の演奏も予定されている。一般の方、とくにオルガン導入を予定しておられる方の参加を勧めます。