東京芸術劇場のガルニエオルガン
4月27日、日本オルガン研究会の主催により、東京芸術劇場のガルニエオルガンの見学会と説明会が行われた。
このオルガンは、ルネッサンス、バロック、モダンの三つの様式のオルガンが集積された世界でも初めてのコンサートオルガンである。約30分、ガルニエ氏自身の演奏で、ルネッサンス、バロックの二つの様式のパイプによる小品を聴いた。気品、奥行き感、それに、繊細さと芯の強さとの微妙なバランス、わが国ではガルニエオルガンはまだ一部の専門家の間にしか知られていないが、この音が彼の感性と技術のすべてを語っているように思えた。ガルニエオルガンの概要を私の理解した範囲でお伝えしたい。

彼はこのオルガン製作の構想を二つの視点からすすめた。まずは、東京というオルガンについての伝統がない街のホールに設置されるということへの認識と、もう一つは、彼がオルガンの歴史から学んだ着想であった。
わが国のホールのオルガンはどうあるべきかという基本的な課題は、これまで何人かのビルダーに問い続けてきたが、明確な解答をうることができないまま今日にいたっている。これに対してガルニエ氏はこの課題を正面から取り上げたのである。
オルガンは音楽の時代的な流れとともに、風土による特色をも背負った楽器であり、キリスト教の礼拝用の楽器として発達し、17,18世紀に頂点を迎えた楽器である。したがって、ヨーロッパでは各地に特色あるオルガンが分布しており、各時代の、また、風土固有のオルガンに接することができる。しかし、今日世界最大の音楽消費都市といわれる東京では、ことオルガンに関しての事情はまったく異なるのである。いくつかのホールにオルガンが設置されているが、ヨーロッパのように、風土や時代の背景から生まれたオルガンではないのである。
時代的な特色として、彼がとくに注目したのは各時代の調律法であった。すなわち、1500年頃までの
ピタゴラスの調律法、宗教改革以降のミーントーン、18世紀末に生まれたバロックの調律法、それ以降の平均率というような調律法の大きな流れである。そしてそれぞれの時代の音楽はその時代の調律法にしたがったとき、はじめて美しく響くのだということが彼の発見であり、オルガン製作の信念となった。現在のコンサートオルガンはパイプの種類こそ、ドイツバロックから、フランス、スペインなどいろいろな様式を取り込んであるが、調律法となると一律であり、ピッチの変更すらできないというのが実情である。ここに、コンサートオルガンといわれている規模だけが大きくなった多目的オルガンの限界があったように思う。彼が現在のホール用のオルガンに必要と考えたのはピッチの可変機構であり、今回、やっとその実現のチャンスが巡ってきたのである。
次のステップは具体的な可変機構である。一つのパイプの中にピッチの可変機構を取り込むということは実際問題として困難であり、ここでそれぞれの様式のオルガンを集積するという今回のオルガンの構想が生まれた。
東京都からの問い合わせに対して、当初、三~四様式の違ったオルガンの集積を考えて、ルネッサンス、バロック、現代の三つのタイプとし、これを鍵盤三つをもった三面のオルガンとして提案した。しかしスペースの制約から、ルネッサンス、バロックをクラシックタイプとして一面にまとめ、もう一面をモダンとし、二面の複合オルガンとして、これを図のように3台のターンテーブルに配置した。
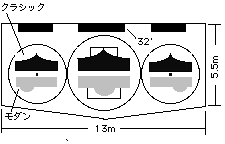

オルガンは上図のように幅13m、奥行き5mのバルコニーに設置されている。オルガンの総重量は55~60トン、モダンとクラシックのパイプ群の間には工事用、および調整用に2台のエレベーターまでが組み込まれている。ブロアーは5台、可変速度のモーターを使用しており、ウインドチェスト50台に連なる。回転時には全体がわずかにリフトアップされ、トラッカーが外れる仕組みである。
クラシックタイプはルネッサンス、バロックの様式のパイプで構成され、3段の手鍵盤とペダルである。ルネッサンス、バロックの切り替えは手鍵盤上のボタン一つで行われる。モダンタイプは手鍵盤5段で、ロマン派を代表するパイプで構成されるが、ラモーなどのフランスの古典ものもこのモダンで対応することにしてある。
このオルガンはクラシック、モダンという二つの顔をもつが、本劇場の建築家、芦原義信氏の意向により、モダンのファサードがオルガンの標準的な設定位置となることとなった。ガルニエ氏の基本的なファサードの形は同心円を75回転したパターンがモチーフとなっている。いまは反射板の背後に隠れて見えないが、いずれその顔を現すであろう。
技術的な問題はペダル用の32フィートパイプの扱いである。パイプは寸法も大きく、重量もあり、回転台への装着が困難であるため、後壁に固定し、クラシック、モダンで共用する。この際のピッチの違いは二つの方法で対応する。まず、鍵盤とパイプの結合を様式によって半音ずらす。鍵盤を半音ずらして440Hzと415Hzに対応するという手法は、すでに彼のポジティブオルガンに用いられている。さらに、右図のようにパイプに二つの送風口をもうけ、ピッチの微調を行っている。低音域では12セントくらいの違いは耳には検知できないとのことである。
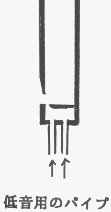
ストップの伝達機構は機械式であるが、その起動は電磁マグネットで、これをコンピューターで制御する。ストップは1000のコンビネーションが可能であり、うち200がオープンで自由に使用できる。コンビネーションスウィッチは手鍵盤の左右とペダルにある。また、助手が外部から作動することも可能である。
質問の一つに、伝統的なメカニカルな伝達機構とエレクトロニックス機器という異質なパートの組み合わせをどう考えるのかというのがあった。彼の見解はオルガンの本質的な箇所はすべて伝統的な手法と材料によっており、エレクトロニックスは制御という周辺部分に限ったこと、故障の場合はそこだけ取り替えればよいという明確な答えであった。
これまで何度かオルガンについての製作意図の話しを聞いたが、このような明快な説明は初めてであった。それでいて、すごいオルガンだ、という印象である。何より音色が美しい。いま工事の遅れが大きな課題であり、ガルニエ氏をめぐる状況は決して好ましいものではない。一日も早く、今日のいざこざが過去の一駒として薄れ、オルガンの美しさのみが評価される日がくることを望んでいる。
モーツァルト時代のミサの復元
5月4日土曜日、国際基督教大学チャペルにて、モーツァルトのミサの演奏会が行われた。いや、演奏会というよりもむしろ、ミサという宗教的儀式そのものの復元であった。取り上げられたのは、彼の《ミサ・ソレムニスK337》ハ長調。これらをミサ通常文とし、1780年3月26日、ザルツブルク大聖堂において行われた復活祭後第一主日のミサを、そのまま再現しようとしたのが今回の試みである。その歴史的考証は、ザルツブルク大聖堂文書館の文書係主任であるエルンスト・ヒンターマイヤ博士の協力を得るという、かなり本格的なものであった。演奏は、過去にもバッハの礼拝式を復元したバッハ・アカデミー合唱団およびオーケストラ、指揮はエックハルト・ヴァイアント氏、オルガンは水野克彦氏が担当、司式は石井健吾神父が行った。
ミサとはカトリック教会の中心をなす礼拝である。全体の構成は音楽によってあらわされたミサ通常文(キリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、アニュス・デイ)と、教会暦や祝日によって変化するミサ固有文(入祭唱、昇階唱、奉献唱など)から成っている。したがって今回は、モーツァルトのミサ曲、および教会ソナタハ長調K336をはさんで、こうした固有文の部分がすべてラテン語で再現された他、グローリアとクレドの部分でも、合唱(本来ならば聖歌隊)が歌う前に、司祭の先唱が行われるなど、演奏会場では味わえない、まさに本来の典礼の中でのミサの姿を浮かび上がらせてくれた。ただし現在、カトリック教会では第2バチカン公会議(1962-65)で定められたミサ以外を行わないことになっているため、ミサの中でも最も重要な部分である聖体拝領については、聖体を使わずに行うという条件で、ラテン語による典礼が許可されたとのことであった。
音楽的には、モーツァルトの先輩格にあたるH.E.F.ビーバー作曲の7声のソナタ(トランペットの合奏による司祭の入堂)や、J.E.エーベルリンの奉献誦を生の演奏で聴けたことは貴重な体験であった。2人は、モーツァルトが宗教音楽の伝統を受け継いだ、ザルツブルクの代表的な作曲家である。しかしまた新たに感じたことは、モーツァルトの音楽の響きの新しさである。とりわけ、合間に歌われたグレゴリオ聖歌、あるいは詩篇の朗読に続いて、モーツァルトの音楽があらわれるとき、同じ宗教音楽でありながら、その響きの違いに初めは耳が慣れなかった。まさに最新の音楽が典礼の中で鳴り響いていた当時こそ、人々はどの様にそれを受け止めていたのであろうか。また、とりわけ教会ソナタは、オルガン協奏曲ともいえるほど、オルガニストがその腕前を披露する華やかな作品であった。当日のミサには、モーツァルト自身がオルガニストとして参加したということであるから、彼の誇らかな姿も頭に浮かんだ。
同時に感じたことは、建物と音楽との関係である。今回の趣旨は、ミサを音楽的に再現することであったため、編成人数、あるいは建築空間とその音響的な再現までには至らなかった。しかし当日配布された詳細なパンフレットにある記述と、大聖堂の内部図によると、当時は聖堂内に4台の壁柱オルガンがあった。これは1859年に撤去され、ようやく今年になってその再建が完了したという。ゴチック様式を始めとして、西洋音楽は常に建築様式とも深い関わりをもって発展してきた。モーツァルトも作曲の際には、こうした音響空間も意識していたことであろう。
全体を聴いて(参加して?)みて、演奏会だったのか、礼拝だったのか、いま一つ曖昧ではあったが、当時の礼拝式の再現という意味ではきわめて貴重な体験ができた好企画であった。(永田美穂 記)
NEWSアラカルト
ウィーン国立オペラ劇場で活躍するTOAディジタル調整卓[ix-9000]の発表会
オペラの殿堂、ウィーン国立オペラ劇場で電気音響設備が積極的に使用されているという意外な事実を知ったのは1983年の9月であった。そこで、トーンマイスターのフリッツ氏にお目にかかり、電気音響設備の拡充の構想を聞いた。彼の一途な努力によって、国立オペラの設備は年々拡充され、それが今回のディジタル卓までを組み込んだ、世界でもっとも斬新な音響設備となったのである。
もう一つの驚きは、ディジタル技術においても、また、舞台音響界においても、後進のTOA社がその共同開発の相手として選ばれたことである。この事は今後の劇場用機器開発について、多くの示唆を含んでいると思う。このディジタル音響調整卓[ix-9000]は昨年の秋からフリッツ氏の手足となってウィーン国立劇場で活躍している。
5月17日、東京の新高輪プリンスホテルにおいて、このディジタル卓の発表会が“TOAサウンドシンポジゥム91”として開催された。当日は作曲家諸井誠氏の「素晴らしきオペラの世界」という講演に引き続いて、フリッツ氏から「オペラと電気音響」という題目で、実際のオペラの場面のテープ再生を交えながら、いろいろなシーンでの電気音響設備の使われ方の実態の紹介があった。しかし残念なことに、肝心のオペラの場面を紹介する録音テープの音質はウィーンのイメージとはほど遠いものであった。