音で音を消す装置
空気や物体が動いて機械的なエネルギーが消費されるとき、その一部のエネルギーは騒音となって放射される。したがって、今の世の中、あらゆる環境で何らかの騒音対策が必要である。ここでは、遮音、防振、吸音などといったオーソドックスな対策とは別に、音を発生させて音を消すという変わった手法二つを紹介する。
マスキングサウンドによる遮音対策
マスキングとはある音によって別の音が聴感的に聞こえなくなる現象をいう。車や航空機などの騒音によって、電話やテレビの音が聞きづらくなることは、日常生活でしばしば経験している。
この現象を利用して、隣の室から漏れてくる話の内容を分かりにくくすることができる。このアイディアを利用したのが“マスキングノイズシステム”で図のように室内に置いたいくつかのスピーカから空調騒音のような気にならない雑音を出して、隣の室から漏れてきた話の内容を分からないようにする仕組みである。アメリカのオフィス環境から生まれたシステムで、マスキング音発生器、アンプ、スピーカがセットとして市販されている。
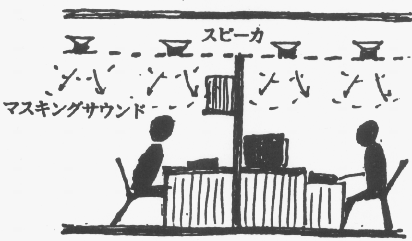
もう10年くらい前のことであるが、某大学が都心から郊外に移転したとき、研究室間で隣室からの音漏れが問題となった。室―室間の遮音性能は都心の古い校舎よりはるかによくなったのだが、引っ越したばかりのキャンパスは夜間ともなるとあまりにも静かで、隣室の話声や電話のベルが聞こえてくるのである。このようなとき、このマスキング装置は有効であった。
室内騒音を少し大きくするだけで、気になる音を聞こえにくくすることができる。遮音壁を追加することにくらべるとはるかに安い騒音対策である。しかし、この装置はどんな場所でも効果があるとはいえない。静かな場所での補助的な遮音対策と考えるべきで、道路騒音がうるさい都心のオフィスには適切ではない。
電子消音装置
周波数が同じ二つの波が出会うと、図のように位相によって強めあったり、弱めあったりする。これを音の干渉という。したがって、スピーカによって、位相が逆の波を発生させ、元の音に加えると、その音を消してしまうことができる。これが電子消音装置の原理である。
この原理による消音システムは昔からいろいろ試みられてきた。変電所のブーンといううなりは波の形がシンプルであるから、干渉を利用するには格好の騒音源であり、試験的な対策が試みられたこともある。しかし、空調騒音のように周波数成分も複雑で、時間的にも変動している騒音を打ち消すには、今日のディジタル信号処理の進歩を待たなければならなかった。
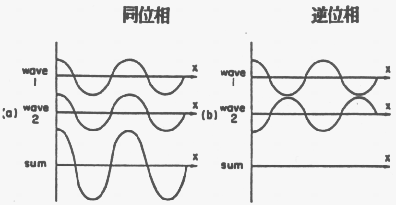
数年前であるが、スピーカで有名なBose社でパイロットのヘッドセットに組み込まれたこの電子消音装置を初めて体験した。この装置は1986年無給油、無着陸の世界一周に成功したボイジャー1号のパイロットの疲労を軽減する目的で開発されたもので、現在は民間用のヘッドセットとしても市販されている。
この種の装置はわが国のメーカーが得意とするところで、最近、国産のメーカーで空調騒音を対象とした電子消音装置が開発され、市販されている。下図は日立プラント建設(株)の電子消音装置である。空気は右上のダクトから左下に向かって流れる。まず、右上のダクト内のマイクロホンでダクト内の騒音を吸収し、この信号をコントローラーで演算して逆位相の音をスピーカから発生させ、音を打ち消すという原理である。説明によれば左下のマイクロホンは消音状態確認用とのことで、この信号もコントローラーにフィードバックしてスピーカの発生音を調整する。
この消音装置の効果は低音域(250Hz以下)に限られること、ダクトのサイズに限度があること(1m×1m)、ある長さの直管ダクト(2.5m)が必要であることなどいろいろな制約はあるが、その消音効果は約20dBとかなり大きい。設計側として一番気になるのはスピーカの寿命、コントローラの安定性である。万一のことを考えると、何らかのバックアップシステムが必要である。スペースなど建築の現場に適応するにはいろいろな問題があると思うが、この装置はいずれ家庭用の空調機にまで組み込まれるであろう。CDを聴くときも気にならない静かな空調が身近になることを期待している。
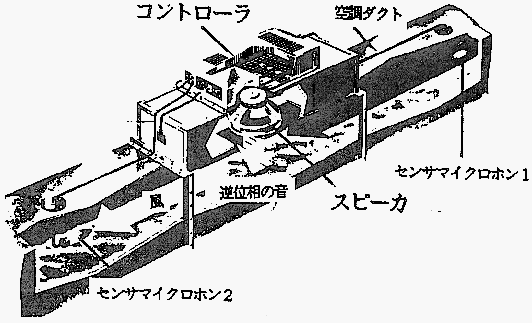
NEWSアラカルト
“宮本忠長の建築”見学会
5月19日、20日の2日間、JIA(新日本建築家協会)関東甲信越支部デザイン部の主催で、“宮本忠長の建築”をテーマとした見学会が行われた。宮本忠長さんは郷土信州の地で実直な建築活動を続けておられるアーキテクトである。その作品には氏の暖かいお人柄が反映されており、建築学会賞、吉田五十八賞などを受賞されておられる。
今回の見学会は宮本さんの代表作品である“長野市立博物館”“小布施町の町並修景計画”を中心に行われた。川中島の古戦場に建つ長野市立博物館は折からの雨で、信州盆地を囲む山並みを背景にした造型を楽しむことができなかったのが残念であった。
小布施町は長野から東15km、千曲川沿いの小さな町である。栗の町として、また最近では、北斎の町として有名である。この町並修景計画の発端は北斎の作品の散逸を防ぐ目的で宮本さんが提案された北斎美術館の計画から始まった。
三代にわたる町長の一貫した姿勢、宮本さんという信州の風土を心から愛しておられる建築家、老舗である小布施堂をはじめとする民間の協力によって、この事業は昭和56年度町並修景事業として発足し62年に完成した。当日の説明によれば、対象面積14,000m2、事業費はわずか5億円という規模の事業であるが、現在この小さな町は年間数10万人にものぼる人を呼んでいる。スケールこそ小さいが、開発一途に走る現代社会が取り残した大事なものをこの修景事業は蘇らせたのである。

この見学会の前夜、久しぶりに松本のハーモニーホールで花房晴美さんのピアノを聴いた。このホールについては何度も紹介したが、公共のコンサートホールとして立派な運営を続けている珍しいホールである。最近、館の人事の入れ替えがあり、以前の運営がすばらしかっただけにその後の経過を心配していたのであるが、オープンの時のあの気風がそのまま引き継がれていることを知り安心したのである。市長の英断によって生まれたこのホールは、それをあずかる人々の企画とサービス、市民の支持によって市民の中のホールとして着実な歩みを続けている。
音響設計という狭い世界の仕事であるが、お役人についてはいろいろな面を見てきた。形式的な管理だけに終始し、主張がなく、責任をとらない、といった共通のイメージの中で、小布施や松本のように施主としてすばらしいお役人がおられることが、仕事をしてゆく上でこれほど嬉しいことはない。宮本さんの情熱と歓びが手にとるようにわかってくる。小さくてもよい、このような本物の拠点が生まれ、またその輪が少しづつ広がってゆくことを願うのである。
見学会は80名という盛況で、19日はこれも宮本さんの事務所によって修復が続けられている湯田中温泉のよろず屋に一泊し、忘れてしまった日本旅館の木の香りとサービスを満喫した。
水戸芸術館、イモージェン・クーパーのシューベルト
4月24日、水戸芸術館開館記念コンサートの一つであるイモージェン・クーパーのピアノを聴いた。オールシューベルトというプログラムに惹かれて、イギリスからの女流ピアニストの演奏会に出掛けた。
開館直後のホールというのは楽器もホールも、また演奏者もなれないために、何かぎくしゃくするのが常である。この水戸のホールについても、はっきりと床が悪いと指摘される方もおり、たった二回のピアノ演奏ではあったが多少気になっていた点もあった。しかし、クーパーの演奏はこんな懸念をすっかり拭いさってしまうほどのすばらしい演奏であった。緻密で深く、しかも流れるようなシューベルト、音の美しさと微妙な音色の使いわけ、至福の一時であった。クーパーの音楽については当日のプログラムに諸石幸生氏の的確な一文があり、サントリー小ホールで行われた演奏の批評については、5月2日の朝日新聞に中河原理氏の、彼としてはめずらしく感動を表に出された記事がある。彼の言葉をお借りすると、“‥‥クーパーで際立っているのは音のきれいなこと、心もち湿り気を帯び、柔らかくみずみずしい響きがする。その澄み切った透明度の高さは格別で、そういう音に乗るとき、シューベルトのチャームはいや増しに増す。とりわけ単音で歌うときの美しさが耳に残っている。”
シューベルトといえば、1989年秋のカザルスホールのジョセフ・カリクシュタインの暖かい演奏も心に残っている。クーパーの演奏はよりとぎ澄まされた美しさのシューベルトであったように思う。ホールの誕生とともに、このような演奏家が身近になってきたことはうれしい限りである。
ハラルド・フォーゲルとフェリスオルガン
ハラルド・フォーゲル氏は北ドイツ生まれのオルガニストで、ゴシック後期から18世紀にかけての鍵盤楽器奏法の研究者として知られている。同時代のオルガンの構造にも詳しく、歴史的オルガンの修復も手掛けられている。わが国のオルガニストで彼の門をくぐった方も多い。
この度、聖グレゴリアの家の招待で来日され、聖路加チャペルのガルニエオルガン、聖マーガレット教会の辻オルガン、フェリス女学院音楽ホールのテイラー・ブーディオルガンなどを演奏された。それらの中で5月7日のフェリスの演奏会は“オルガン、その音楽の魅力”というテーマの解説付きのコンサートで、16世紀から18世紀のバッハにいたるまでの作曲家5人の作品を例に、声から楽器へと発展していったオルガン音楽の推移を系統的に解説された。
このフェリスのオルガンは、Taylor & Boody というアメリカのビルダーの作品ではあるが、演奏者の背後にもう一組のオルガン(Ruckpositiv)をもった歴史的なタイプのオルガンである。その音は気品が高く、しかも輪郭が明確である。フォーゲル氏は時には人力による“ふいご”の送風を使い、また、Ruckpositivを用いて奥行きのある響きを作りあげていった。最後のバッハのパッサカリアは、久しぶりに壮大なバッハを聴いた思いがした。
このオルガンのオープンは今年の末である。その時点でホールとオルガンの紹介をしたいと思っているが、幸いなことに7月7日(土)10時からレクチャーリサイタルが行われる。ぜひ聴いていただきたいオルガンである。なお、聴講券は1,000円、ご希望の方はフェリス女学院大学音楽部(045-662-4521)まで申し込まれたい。