
桜美林大学の新しい礼拝堂とパイプオルガン
今年3月、桜美林大学(東京都町田市)に新しく完成した「荊冠(けいかん)堂」の献堂式が執り行われた。本施設は、パイプオルガンを備えた600席の礼拝堂、多目的ホール、事務室からなる施設で、学校法人桜美林学園の創立60周年記念事業の一環として、これまで学園のシンボルとして長く親しまれてきた旧荊冠堂(ヴォーリズ設計、1959年完成)を建て替えたものである。礼拝のほか、講演会やパイプオルガンをはじめとする音楽コンサートの会場にも利用される。設計は古橋建築事務所、施工はスルガコーポレーションである。
室内音響設計
礼拝堂は渦巻き状の平面形をもち、壁は聖壇下手から会衆席後部、聖壇上手へと、少しずつその半径を小さくしていく。それに併せて天井は徐々に高くなっていき、中央部でトップライトに至る。そこに集う人々を中心に向かって包み込みながら天へと導くような空間である。その形態は外観にも見て取れる。
室内音響面での課題は、円形に起因する音の集中やエコーの回避であるが、気積が約7m3/席と少ないため、響きを確保するためには吸音材の使用を避けたい状況であった。そのため音の集中やエコーをすべて室形状で解決する必要があり、3次元シミュレーションによる検討を重ねた。最終的には、円形の意匠を維持するために内装面を音響的に透明と見なせる木リブで仕上げ、その背後に躯体の円形を崩すように壁を設置した。その壁はパイプオルガンの低音を響かせるために、無石綿繊維混入石膏板10mm厚×4層貼りとし重量を確保した。また木リブも、断続的に円形が形成されるのを避け、かつ特定の周波数音の強調(リブ鳴り)を防止するために、前面にテーパーをつけ、その向きとリブの幅・奥行き・間隔を変えた数種のものをランダムに並べた。


空席時の残響時間は1.5秒(500Hz)で、中音域より低音域の響きが長い特性が得られている。
電気音響設備設計
スピーカは拡声音の到達範囲を会衆席に限定し、エコーの発生が懸念される円形の壁への音の入射を最小限に抑えるために、垂直方向の音の指向性が鋭い小型ラインアレイタイプとした。このタイプのスピーカは細長い形状のため、木リブの内装とも調和しやすいと考えた。スピーカは聖壇両脇の1階と2階レベルに配置し、聖壇側から音が聞こえるように配慮した。電気音響設備は適切に操作しないと性能が十分発揮できないため、操作部を聖壇近くの扉脇に設置し、拡声音を聞きながらマイクの音量調整ができるようにした。献堂式での学園長の挨拶では、明瞭で自然な音質と十分な音量が得られていることを確認した。
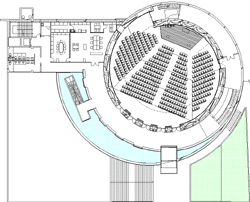
パイプオルガン
2階バルコニーに設置されたパイプオルガンはスイスのオルゲルバウ・フェルスブルク社製で、ストップ数は33個、3段手鍵盤と足鍵盤を備える。楓の明るい色彩とシンプルなデザインにより、礼拝堂の聖壇や椅子との調和が図られている。献堂式に続いて行われたパイプオルガン奉献コンサートでオルガニストの今井奈緒子さんが演奏されたが、その音は明るく張りがありながらも優しく繊細で、心地よいものだった。
本施設が、学内外のコミュニティ形成の場として、旧荊冠堂と同じように長く親しまれ続けることを期待したい。(内田匡哉記)
桜美林大学HP http://www.obirin.ac.jp/
NHK技術研究所旧音響研究部の業績の紹介
筆者がNHK技術研究所に入局したのが1949年、音響研究部が誕生したのが1951年6月である。音響研究部は音響機器研究室、建築音響研究室、低周波回路研究室、音響効果研究室、録音研究室、音響材料研究室の6研究室の構成であった。
当時はまだラジオ、それもAM放送の時代である。受信器は並4といわれる4本の真空管によるセット、スピーカはマグネチックスピーカ、マイクロホンはカーボンマイク、レコードはSP、再生機は機械式の蓄音機が主流の時代であった。磁気録音機はまだ登場せず、番組制作はすべて生放送であった。まさに、大政奉還直後の明治の初期の状態である。
このような混迷の中で誕生したNHK技研音響研究部であるが、その存在と活動は当時まだ芽生えたばかりのわが国の音響界の発展の大きな原動力となった。それぞれの分野で当時先端をゆく技術開発、設計手法の確立、学会への貢献などわが国の音響業界、学界への貢献は輝かしいものであった。これは、ひとえに、音響研究部長として活躍された故牧田康雄氏の研究に対しての一貫した指導理念によるものである。
しかし、この音響研究部は1970年8月に解散した。これを機会に幾人かの同僚がNHKを去った。筆者もそのひとりである。
当時の音響研究部に関わりのあった者、職員、実習生、アルバイトなどが旧音響研究部の会を組織し、毎年9月、青山の青山荘に集まり、旧交を温めている。それとは別に、2004年1月以降、2ヶ月に1度のペースで、各研究室有志があつまり、それぞれ業務の実態の紹介から、やりのこしたこと、もし音響研究部に身をおくとしたら、どんなテーマの研究を取り上げるべきか、など、様々な形で、音響研究についての思いを語りあっている。この会合で分かったことは、隣の研究室の実態について、一部の成果は分かっていたものの、その生みの苦しみなどは全く知らなかったということである。これらは、いずれ、何らかの形で、後生に残しておきたいと考えており、現在、思案中である。
さしあたり、本ニュースの一端をかりて、各分野での成果を紹介してゆきたいと考えている。まず、音響機器研究室でもっぱら、マイクロホンの開発に従事してきた溝口章夫氏に接話マイクロホンの開発の経緯について執筆をお願いした。(永田 穂記)
溝口章夫氏 略歴
- 1929 長野県生まれ
- 1951 山梨工業専門学校卒
- 1952 NHK入局
福井放送局勤務 - 1959 NHK技術研究所勤務
- 1983 NHK退職
アイワ株式会社入社 - 2005 アイワ株式会社退職
- 2006 三研サンケンマイクロホン株式会社入社
- 2007 三研サンケンマイクロホン株式会社退職
- 学位:工学博士(1977年 名古屋大学)
マイクロホン開発の歴史(1)
私が、NHK放送技術研究所在職当時(1959年〜1983年)開発・実用化した放送用マイクロホンの代表的なものについて、逐次ご紹介したいと思う。
まず、初回はあまり知られていない接話マイクロホンを取り上げてみる。ここ10年来、スポーツ放送などで、ヘッドホン本体の下部から細い支持棒が口元まで伸び、その先にマイクロホンが取り付けられている特殊なマイクロホンを見かけるようになってきている。このようなマイクロホンは、口元近くで使用されるので接話マイクロホンと云い、周囲騒音の大きい場所で、話者の声だけを明瞭に収音できる特長がある。このように、首から上に取り付けられた接話マイクロホンは、今でこそ一般化しているが、その開発は1964年、いまから44年前の東京オリンピック放送にさかのぼる。
オリンピック放送では、内外の多数のアナウンサーが、放送席に隣り合って座り、実況放送を行なうので、普通のマイクロホンを用いると、主たるアナウンサーの声に両隣のアナウンサーの声が混ざってしまい、放送にならない。
ところで、接話マイクロホンについては、当時、リボン形(RCA)およびムービングコイル形(BBC)などの実用製品が開発されていたが、形が大きく重いため、手に持って使用するには口とマイクロホンの距離を一定に保つのが難しく、音質や音量が変化する欠点があった。また、ローマオリンピック大会に使用された接話マイクロホンは、ムービングコイル形であるが、鼻の下にマイクロホンの上部を当てて使用するような構造になっていて、マイクロホンと口の距離を一定に保つようにしていたが、使い勝手の面でかなりの苦情があった模様である。

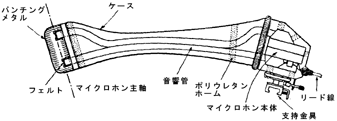
そこで東京オリンピック放送では、当時、世界的にも初めての試みとして、ムービングコイルマイクロホン本体を図1に示すように帽子に取付け、さらに、図2に示すように振動板の両側から2本のパイプを口元まで延長し、両指向性で接近収音する構造とした。パイプの先端には、フェルトを取付け、図3に示す構造のフェルト押さえキャップにより、フェルトの音響抵抗を変えられるようにして、パイプ内の反射波による特性上の起伏を最小限にしている。また、マイクロホン出力をON・OFFできるスイッチボックスを備えている。
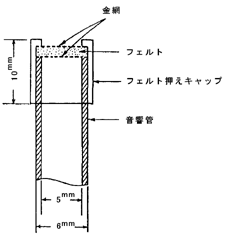
この両指向性接話マイクロホンの感度周波数特性を図4に示す。同図が示すように、収音距離が2cmの近距離では、ほぼ平坦特性とみなされるが、50cmに離れると、2kHz以下の周波数で、周波数に反比例して低下する特性になる。また、いかなる収音距離でも指向性は両指向性で、90°方向での感度は零になる。つまり、8の字の指向性パターンになる。
このように、遠距離感度が近距離感度に比べてかなり低下する効果は、大きな防騒音効果となり、これに加えて両指向性という指向性と、収音距離の違いによる音の大きさの違いなども、極めて大きな防騒音効果をもたらす結果となった。この接話マイクロホンで収音される両隣の人の声は、ほとんど聞き取れないぐらい小さなものとなった。この接話マイクロホンの製品化は、三研マイクロホン(株)が担当し、東京オリンピック放送では約300個が作られ各国の放送関係者に貸し出され、マジックマイクと云われるなど、大きな成果をもたらした。
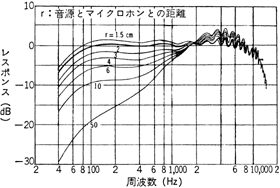
なお、この接話マイクロホンの開発は、オリンピック開催の年から3年前に着手し、国民体育大会をはじめ、マラソン、ラグビーなどの各種スポーツ番組で試用し、現場の意見を盛込み、さらに手直しをして最終形態にまとめたものである。


次に、1972年に行われた札幌冬季オリンピックの放送用に開発・実用化された接話マイクロホンをご紹介する。このマイクロホンは、小型軽量化を目的にコンデンサーマイクロホンとし、図5に示すようにヘッドホンに取り付けヘッドホン本体の下部から細いパイプを延ばし先端にマイクロホンを取り付けたものである。装着した状態を図6に示す。また、このマイクロホンの感度周波数特性を図7に示す。
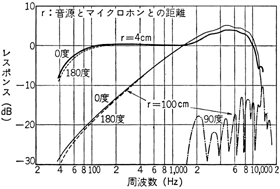
指向性は両指向性で、図のr = 4cmの近距離特性に比べてr = 100cmでの遠距離特性は、1500Hzから周波数に反比例して低下する特性になっている。この接話マイクロホンの実用化にあたり最も配慮した点は、寒冷地での使用に十分耐えるということであった。当初、試作品を北海道で試用したところ、外で使用して温かい室内に持ち込むと結露現象のため極めて大きな雑音を発生する現象にみまわれた。この対策としては、振動膜に近接して取り付けられている背電極の周辺や、絶縁物の周辺などにシリコンラバーを充填して、完全な絶縁状態を保つようにした。また、温度に対する感度変化は、−20℃〜40℃の範囲で2dB以内、湿度による感度変化も、45%〜90%の範囲で2dB以内という結果を得ている。
この接話マイクロホンは、オリンピック開催日から3年前に開発を始め、試作、改良を重ね、1971年2月に札幌で実施された冬季国際スポーツ大会で試用され、使い勝手の面で好評であった。翌年の冬季オリンピック放送では、製品化を三研マイクロホン(株)が担当し、300個が製造使用され好評を得た。(溝口章夫記)