
マリインスキー・コンサートホールのオープニング
2005年5月発行のニュースでお知らせしたサンクト・ペテルブルグ(ロシア)の新しいコンサートホールが、2006年11月29日にオープンした。新ホールは1100席規模の中型コンサートホールで、芸術総監督であるヴァレリー・ゲルギエフ率いるマリインスキー劇場に所属する。同劇場のオーケストラ(別名:キーロフ・オーケストラ)を中心とした室内楽、ソロ等の各種コンサートの本拠地となるとともに、外部からの客演コンサートも計画されている。建築設計はパリのアーキテクト”Fabre/Speller/Pumain Architects”が、そして工事は地元ロシアのゼネコン”NEVISS-Complex”が担当した。永田音響設計はその設計から監理、測定までの一連の音響設計を担当した。

この新コンサートホールのプロジェクトは、2003年9月にマリインスキー劇場に所属する倉庫(劇場から数ブロック離れたところにある建物)に火災が発生し、格納されていた舞台装置や衣装などそのほとんどを焼失してしまったことに端を発する。ゲルギエフが考えたことは文字通り「災い転じて福となす」、すなわち、消失した倉庫の跡地を利用して新しいコンサートホールを建設することであった。現在、マリインスキー劇場に隣接して新しいオペラ劇場(2000席規模、建築設計:Dominique Perrault)の建設計画が進行中で設計段階にあり、このプロジェクトが「Mariinsky2」と呼ばれていることから、新コンサートホールのプロジェクトは「Mariinsky3」と名付けられた。Mariinsky2がロシア連邦のプロジェクトとしてその巨大な官僚機構の管理のもとに進められ、そのプロセスにかなりの時間が掛かっているのに対して、Mariinsky3はゲルギエフ個人によって各方面から集められた寄付金を基にマリインスキー劇場独自のプロジェクトとして進められた。設計期間は2004年8月〜2005年4月の約8ヶ月。そしてそれに続く工事期間は2005年5月〜2006年6月の約14ヶ月という通常では考えられないスピードである。現場における工事は、冬季期間も含めて24時間、昼夜を通して進められた。2006年6月に予定どおりの完工とはならなかったものの、ほぼ9割方の工事を終えて実際にオーケストラをステージに入れたリハーサルが行なわれた。それから5ヶ月の仕上げ工事を経て、2006年11月の正式オープンの運びとなったものである。
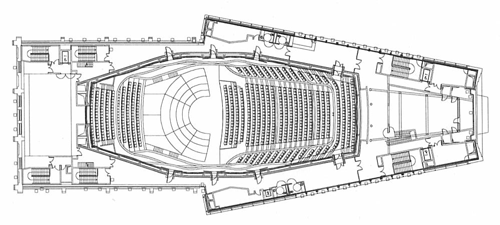
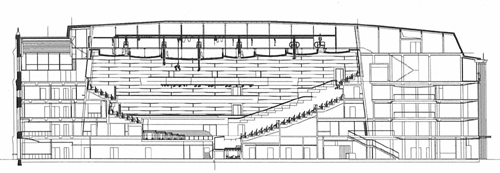
新ホールの室寸法は、幅:約22m、長さ:約52m、天井高:約14.5m(ステージ床〜天井)である。平面、断面形状をFig- 1〜2 に示す。室形状はシューボックス型の形状を基本としながらも、ステージの周辺にも多くの客席を配置し、1Fメインフロアの客席勾配をかなり急にするなど、既存の著名なシューボックス型コンサートホールとは多少趣を異にしている。特に1Fメインフロアの急な客席勾配は、多くの客席からステージ全体が見渡せるように配慮した結果であり、客席とステージとの一体感、ホール空間における臨場感の確保に大きく寄与している。
ホール内装としては、天井、壁、床とも木材を使用し、音響的に必要な質量を確保することに腐心した。特に天井木材の厚みは約20cmにも及ぶ。壁面には合計約230m2の有孔ボードを分散配置し、その背後にグラスウール吸音材を設置した。しかしながら、実際に必要な吸音面の大きさについては、オーケストラによるリハーサルを通じた聴感的な印象も含めた判断によって調整できるよう、吸音材を取り外し可能な構造とした。最終的には壁面に配置した調整用の吸音材のほとんどを撤去した。その結果、ホール内における吸音面は客席部分のみとなっている。空席時における残響時間の実測値は約2.1秒(500Hz)、この測定結果から推定される満席時の残響時間は約1.9秒(500Hz)である。
オープニングに先立って、弦楽器、管楽器、ピアノ、男声、女声、等々の各種ソロ、アンサンブル、そして最終的にはフル・オーケストラによる試奏、試聴が行われた。その結果、ハープや弦楽器ソロによるピアニシモからフル・オーケストラによるフォルテシモまで、あらゆる大きさの編成、音量に対して、幅広く適応できる高い音響性能が実現されていることを確認した。基本的に良く鳴るホールであり、客席の隅々まで十分な音量が確保されている。ホール空間が豊かで暖かい響きによって満たされる印象の一方で、アンサンブルはクリアに聞こえ、各楽器が明瞭に聞き分けられる。ステージにおける演奏者達の反応も良く、自分の音や他の楽器の音が良く聞こえるとの多くのコメントが寄せられている。マエストロ・ゲルギエフ自身にも十分満足してもらうことができた
オープニング公演は、リムスキー・コルサコフによるスペイン奇想曲を皮切りに、チャイコフスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、等々のオール・ロシアン・プログラムが3時間近く繰り広げられ、ストラヴィンスキーのバレエ組曲”火の鳥”で締めくくられた。今後のコンサートのスケジュールとして、さし当たっては月2〜3度の公演が徐々に増やされていく予定で、今年6月の白夜音楽祭にてフルに使用されることになっている。(豊田泰久記)
国際騒音制御工学会議(Inter-Noise 2006 )
国際騒音制御工学会議(インターノイズ)は、毎年、世界中のいろいろな国で開催されており、今年はアメリカと日本の騒音制御工学会の主催で、12月4日〜6日の3日間、ハワイのシェラトン・ワイキキホテルで開催された。インターノイズ開催の前、11月28日〜12月2日には、やはりアメリカと日本のそれぞれの音響学会のジョイントミーティングが開催されており、音響に関する大きな会議が連続する形となった。講演発表の前日、オープニングの式典がホテルの大会議室で、また式典後、オープニングパーティが前庭で開催された。パーティではフラダンスとハワイアン演奏が行われ、パーティに花を添えた。

発表は騒音や振動に関する研究発表が主で、各種騒音源の調査報告、騒音・振動対策の方法、遮音材料等の各種音響材料の特性など、全体で24のセッションが設けられており、招待講演を含めて約680件の発表があった。今回はハワイでの開催とあって、やはり日米の参加者が多かったが、遠くヨーロッパからの参加者もいて、どの会場も盛況であった。
永田音響設計からは、石渡智秋が「Results of field measurements of generated sound of Japanese drum “Taiko” and consideration towards its sound insulation」のタイトルで、和太鼓の発生音レベルの測定結果および室間の遮音性能に対する受音室での透過音の聴感的な印象について報告した。
インターノイズでは、国際的レベルでの音響に関わるテーマについて調査研究を行う技術検討グループ(Technical Study Group)が設置されており、現在6つのTSGが活動している。このような国を超えた規準作りの一環として、各国の騒音・振動の規制に関するワークショップが1日目に開催され、9カ国の代表の方から報告とそれに対する質疑応答が行われた。日本からは環境省の方が環境基準や騒音規制について報告した。各国の規制にあたってのバックグラウンドの違いもあって、かなりつっこんだ質疑が行われた。このようなワークショップを繰り返し、その結果を世界的な騒音規制の基準作りに反映していくということである。
また、毎朝、通常の講演の前には “Distinguished Lecture” が開催され、合計3件の講演が行われた。2日目には鉄道総合技術研究所の方が新幹線騒音の低減について報告があった。これらの講演以外に、騒音・振動の測定機器や遮音・吸音材料の展示コーナーもあり、こちらも連日にぎわっていた。
ワイキキは、ちょうどホノルルマラソンの一週間前ということもあって、町を歩くと、走っている人たちをよく見かけた。季節もちょうどよく、ワイキキの浜の散歩は疲れた耳と頭のリフレッシュには格好だった。(福地智子記)
本の紹介 「グランド・オペラ」−オペラ劇場の歴史を読む−
アントニー・ギシュフォード編 三浦淳史・中河原理訳 音楽之友社 1975年発行
当社の最寄りである地下鉄本郷三丁目駅の近くに『大學堂』という古書店がある。永田によると、元は東大赤門の前にあったらしい。大學堂には風俗文化・芸術関係の本も多い。もう、売り買いに来る学生も少なくなって…という店主の嘆きを尻目に古本や古雑誌の山をひっくり返しては立ち読みする。その古本の中から発見した一冊が「グランド・オペラ」という本書である。1975年発行なので古書でしか入手できないが、オペラの歴史を歌劇場という視点から解説した、興味をひくものであったので紹介する。
この本によると、オペラはルネサンス後期の16世紀末、伊フィレンツェで詩人や音楽家による議論と実験活動「カメラータ」から生まれたとある。ちょうどその頃、歌舞伎が出雲の阿国(おくに)の踊りで始まったとされている。日本は各地の戦乱が落ち着き、安定した江戸時代(1603-1867)に入る前後のこと。その後、欧米でオペラが隆盛を誇る数百年の間は、幕府の鎖国政策もあって諸外国との交流はほとんど絶たれ、オペラや西洋音楽に親しむのは明治維新後となる。日本で最初のオペラ上演は1894年の『ファウスト』とされている。それから百年以上経て、1997年に新国立劇場というオペラの殿堂が完成したのである。
ヨーロッパ各地では、まず宮廷歌劇場が次々と建設されている。最初は、やはり王侯貴族や富裕層の楽しみであったようだ。宮廷歌劇場は、700-800席程度と小規模なものが多いが、18世紀中期から19世紀初頭の産業革命のころには、多くの一般市民がオペラに通うようになったせいかナポリ(サン・カルロ)、ミラノ(スカラ)、ベルリン、ミュンヘン、ドレスデン、バルセロナ(リーセオ)、ウィーン、パリ(ガルニエ)など1500席以上、2000席前後の歌劇場が次々と建設されている。スカラ座は建設当初の1778年には3500席もあったという巨大さである。1792年に開場した伊フェニーチェ劇場では、すでに設計競技(コンペ)を行なったとある。そして設計者は、劇場の出来について王様や市民から批判を浴びることが多く、中には非業の死を遂げた人もいたらしい。照明はろうそくや灯油ランプであったために、ほとんど数回は火災で焼け落ちて、最後にはご存知の通り、第二次世界大戦の爆撃を受け(独・伊)、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場でさえ1892年に全焼して、再建されているという歴史には圧倒される。もちろん、20世紀初頭の君主制の終焉や第一次大戦、革命、世界恐慌などの経済不況もくぐり抜けてのことであるから。
本書には、歌劇場に深く関わる作曲家や指揮者についても、詳しく記されている。その中で印象的なのは、音楽監督や芸術監督の役割である。パトロンである王侯貴族や富裕層とのやり取り(資金集め)から作曲の依頼、オーケストラの育成、歌手との交渉、美術や道具類の発注など多岐にわたっている。オペラ劇場の歴史は、これらを実行する有能なマネージャーに支えられた400年だったのである。総合芸術と呼ばれるほどの作品は、得てして独裁的な地位を与えられた天才的な人でなければ実現できないと私には思われる。もちろん、現代ではこれがもっとも困難であることも事実なのだが。(稲生 眞記)
[“Grand Opera” 1972 Weidenfeld and Nicolson 社刊]