最近のホール事情
バブル経済の崩壊で大型プロジェクトの縮小、建設の延期など、一段の冷え込みが伝えられている今日の建設界ではあるが、公共文化施設の建設はむしろ盛況である。最近のホール事情を紹介したい。
文化施設の大型コンペ
昨年から今年にかけて、札幌市音楽専用ホール、新潟市民文化会館、富山市芸術文化ホール、福井県立音楽堂、びわ湖ホール等の大型文化施設の設計競技が相次いで行われ、3月末までに設計者が決定した。ホールの構成、規模は様々であるが、大小のコンサートホール、あるいはコンサートホールと演劇ホールとで構成されるものが殆どである。ところで、これらの施設の中心となるコンサートホールであるが、その設計条件として、シューボックス型の他に、ワインヤード型(札幌市音楽専用ホール、新潟市民文化会館)が指定されたことも大きな特色ではないかと思っている。ワインヤードがやっと市民権を得たという感じである。サントリーホールの実績というのはやはり大きいのである。
東京、名古屋、京都、熊本などについで、2~3年後には主要都市に大型の複合文化施設がオープンする。運営の問題が一層クローズアップすることであろう。
コンサートホール、あるいはクラシック音楽を主目的とした多目的ホールの誕生
コンサートホールの建設の勢いにのって、大都市の周辺地区、地方の小都市にもコンサートホール、あるいはクラシック音楽指向の多目的ホールの建設が次々と進められている。最近オープンしたばかりの施設としては、埼玉県和光市民文化センター“サンアゼリア”がある。建築設計は安井建築設計事務所、この施設には1,286席のクラシック音楽主目的の多目的ホール(大ホール)と平土間の小ホールがある。大ホールは側壁の開き角度を小さくしたこと、天井高を十分とったこと、天井開口部を極力小さくしたことが特色である。
4月10日から5月末日までオープニングの記念公演が行われている。4月11日、ベルリン室内管弦楽団の演奏を聴いたが、響きはコンサートホールといってよい響きであった。それに、入場料がS席で4,000円という低料金である。5月31日のパドゥラ=スコダの演奏会もS席3,000円という料金である。願わくは、あまりポピュラーに流れない、これはと思わせるプログラムを時々でよいから企画して頂きたいと思う。この種のホールの大きな課題だとは思うが。
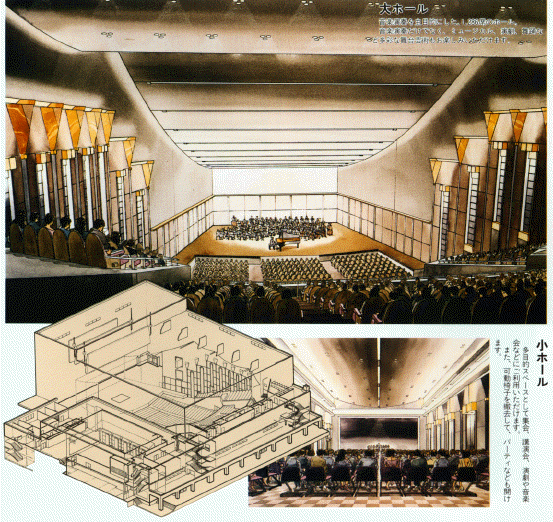
この施設は川越街道からちょっと入ったところ、駐車場はたっぷりしており、車で行くには便利なホールである。
チケットは全国のチケットぴあでも扱っている。お問い合わせはtel:048-468-7771 和光市民文化センターまで。
オープニングを4月21日に迎えるホールとして、横浜市緑区、東急田園都市線青葉台駅前に建つ“フィリアホール”がある。建築設計は1990年まで当事務所に在席していた山本剛史氏(現在エイ・アンド・エイデザイン)である。
このホールは青葉台東急百貨店5階にできる民間の500席の小コンサートホールであるが、横浜市緑区の区民センターという別の顔をもった珍しいホールである。東京のベッドタウンの文化施設として、官民の運営が今後どのようなバランスの中ですすめられてゆくのか、興味のあるところである。
ホールの特色は多様な催し物を考慮して室容積を多めにとり音量に対しての余裕をもたせたこと、側壁にカーテンによる残響可変装置を設置したことなどである。
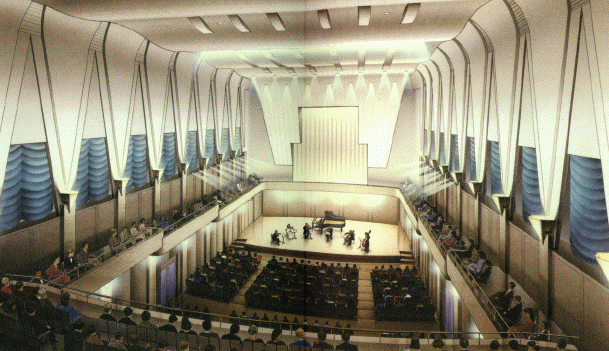
オープニングシリーズは5月1日から31日まで15公演が決まっている。すでにいくつかの公演のチケットは売り切れとのこと。チケットの問い合わせはtel:045-982-9999 フィリアホールチケットセンターまで。
今年の秋のオープニングであるが、建物が竣工しているホールがいくつかある。中野区もみじ山文化センターもその一つである。建築設計は岡田新一設計事務所で、1,280席の音楽、演劇の両立をはかった多目的ホールと図書館という組み合わせの施設である。
詳細の報告は後日にするが、音響設計の課題はホールと図書館との遮音対策、音楽と演劇という合い容れない催し物への対応をどうするのか、という点であった。図書館にはマスキング装置を設置、やや広がった平面形のホールには壁、天井に思い切った反射面を、側壁に吸音調整用のカーテンを建築デザインとの調和の中で設置してある。
4月7日の午後、若杉弘氏指揮の東京シティフィルのリハーサルに立ち会った。空席の残響時間2.5秒というライブさに一瞬驚きがあったが、指揮者、演奏者とも弾きやすいということでのびのびとした演奏で、慣れるとともにライブさがかえって心地よかった。

その他今年中にオープンする施設としては、旭川市クリスタルホール、碧南市コミュニティセンター、玉村町(群馬県)にしきのホール、アイリッシュパーク(滋賀県高島町)、北九州国際交流センターコンサートホール等がある。これら各ホールの詳細は逐次本紙で報告の予定である。
かげりを見せたクラシックコンサート
現在のクラシックコンサートブームが果たしていつまで続くのだろうか。これはホールに関わる者の共通した関心事ではないかと思う。たしかに、最近のコンサートブームにかげりが見え始めたことは、なんとなく肌で感じていたが、4月6日付の日本経済新聞朝刊の『文化往来』の欄に“やはりというべきか、クラシックコンサートの入場者がここにきてガックリ減っている”という書きだしで、マゼール指揮のバイエルン放送響、チェルビダッケ指揮のミュンヘン・フィルのチケットの売れ行きがかんばしくないことを報じている。このミュンヘン・フィルはブルックナー中心のプログラムだったが、最近、曲目がポピュラーなものに変更されたことを聞いた。
1万、2万というチケットが発売とともに売り切れてしまうという、かつての現象の方がむしろ異常というべきであろう。この『文化往来』も次のような言葉でしめくくっている。“だが、ものは考えよう。直前でも人気公演の切符を入手しやすくなったし、広告ばかりが目立つ分厚いプログラムが姿を消した。清貧の時代、本物の愛好家だけが集う親密なコンサートがあちこちに生まれている。”
第5回日本オルガン会議に学んだもの
先月号でお知らせしたように、3月31日の夕方から4月3日の昼まで、日本オルガン研究会主催の第5回日本オルガン会議が東京、横浜の4会場で行われた。今回のメインテーマは“19世紀のオルガンをめぐって”である。オルガン会議としては初めて、アメリカからオルガンビルダーとして、フィスク社のスティーブ・ディーク氏、フランスからオルガン学者、オルガニストでもあるクルト・ルーダース氏の二方を招待し、演奏だけではなく、講演会、シンポジゥムのパネラーとして登場していただいた。会議の詳細はオルガン研究会からの報告書をまつことにして、ここでは筆者の印象を中心に報告したい。
クルト・ルーダース氏の演奏と講演「19世紀のオルガン」から
クルト・ルーダース氏は現在国際オルガン建造家協会事務局長、カヴァイエ=コル教会主宰、パリのサンテスプリ改革派教会のオルガニストという多彩な肩書きの専門家である。会議の初日、わが国ではもっともカヴァイエ=コル様式にそっているといわれている新宿文化センターのケルンオルガンで19世紀のオルガン曲が演奏された。甘美、幻想、色合いの豊かさなどロマン派のオルガン曲のエッセンスを感じさせる演奏であった。

ルーダース氏の講演は、まず“ロマンチックとは何か”という問いから始まった。そして19世紀から今世紀にかけてのオルガン史の概要を当時の社会情勢とからませながらスライド、あるいは、テープ再生をまぜながらの説明であった。
つづいて、今世紀初頭にはじまったオルガン運動がもたらしたもの、また、その過剰な反動の現状についての警告が結びとなった。
シュバイツァーの著書が契機となって、19世紀のロマンチックオルガンの否定、バッハへの復帰を掲げて始まったオルガン運動の結果生まれたのがドイツのネオ・バロックのオルガンである。戦後のわが国のオルガンの多くがこのネオ・バロックオルガンであった。
しかし最近また、このオルガンに対する反動が現れており、フランス系統のオルガンが脚光を浴びている。聖堂の楽器として発達してきたオルガンではあるが、意外と潰し合い、否定の歴史が繰り返されてきたのである。ルーダース氏はそれぞれの時代に生まれたオルガンにはその必然性があり、過去のオルガン運動が招いた愚行を繰り返すべきではないことを強調していた。そして今、われわれが今後のオルガンに対してあるべき態度は、sensitive(敏感)であること、clever(賢明)であること、そして最後にmodest(謙虚)であること、とくに最後の“謙虚さ”はわが国のオルガン界に注がれた言葉のように思えた。
ディーク氏の講演から、フィスク社の理念とフィスク氏について
ディーク氏が所属するフィスク社の創設者故フィスク氏は、当時商業オルガン全盛のアメリカで始めて歴史的オルガンの建造に取り組まれたビルダーである。本人は物理学を専攻されていただけに、ヨーロッパの伝統工芸的なビルダーとはちがった観点でオルガンを手掛けたのではないだろうか。現在でも軽い鍵盤機構の開発、スウェル機構の音量変化の範囲の拡大など、技術革新をこのフィスク社は続けている。講演会の席でも、新しい機構の紹介があった。
フィスク氏はたんにオルガン職人ではなく、“He was a great man.”といわれているように、人間味溢れたいい意味での大親分であったようで、多くのオルガンビルダーが彼の工房から輩出している。ルーダース氏もフィスク氏の次のような言葉を紹介した。“オルガンビルダーは自分の頭の中に鳴っている音を実現することです。”
昨年フィスク社を尋ねた時の印象であるが、工房の殆どの人がオルガンを弾く。オープンで、技術レベルで何の抵抗もなく話しあえる雰囲気が心地良かった。音楽に対しての感性と、技術への関心がうまくバランスしている工房であった。
オルガンとホール音響、筆者が述べたかったこと
「オルガンをめぐる空間の変遷」、これがシンポジゥムで筆者が予定していたテーマであったが、時間がなく、予定していた内容を伝えることができなかった。本会議の舞台である19世紀はL.Rayleigh卿、W.C.Sabin先生の活躍で近代音響学が誕生した時代でもある。教会からコンサートホールへとオルガンの演奏空間にも大きな変動がもたらされた時代でもあった。いま、コンサートオルガンを考える上で、この空間特性、オルガンの設置条件の違いは興味あるテーマである。筆者はこれら目にみえる条件の違いのほかに、音環境の違い、人間と音楽との関わり合いの違いなども無視できない条件ではないかと思っている。
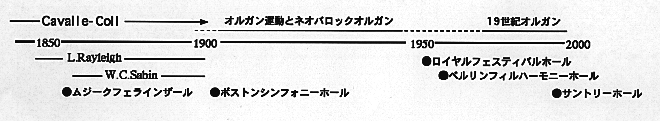
当日、会場の若いオルガニスト、W・ヴオルフ=ヴィーガントさんから鋭い質問を受けたことも忘れられないひとコマであった。質問は歴史的な聖堂の復元は可能かどうかという内容であった。演奏空間というのは楽器よりは感性から遠い位置にあるだけに、楽器の場合よりは、より近い復元は可能であろう、というのがその時思い付いた回答であったが、その後、進んだ説明はまだ思いつかない儘である。