ホールの音は変わるのか
サントリーホールがオープンしてまだ2年にもなりませんが、最近、音が変わったという声をいろいろなところで聞きます。中には“いったいどこをどう直したのか?”とまじめに聞いてこられる方もおられます。舞台の後壁はもともと表面が木のパネルなのですが、場所によっては周囲の大理石と同じように見えます。大理石を何時木に換えたのだ、などの質問もありました。オープン以来ステージ反射板の調整はしましたが、あとは何もいじっておりません。
ホールの音が年月とともに変わることは、これまでもいろいろなホールで聞きますし、私自身も経験しています。NHKホールがそうですし、サントリーホールも当初感じたパランスの悪い響きを最近では聞かなくなりました。
ホールの音が変わることの原因としてまず考えられるのが、演奏者がホールを使い慣れるということです。とくに響きが短い多目的ホールや講堂で弾き慣れた楽団や演奏家が、急に残響の長いホールで演奏した場合。また、サントリホールのようなオープンステージに近い舞台で演奏した場合、自分の音が分からなくなったり、他のパートの音が聞きとれなくなったり、戸惑われることは当然だと恩います。聴いている方にもその雰囲気が伝わってきてけっして楽しめません。
福島市音楽堂や松本市のハーモニーホールでもオープン当初はこんなホールでは演奏できない、というような声を何度も聴きました。オープン当初のごたごたにぷつかるたびに、筆者は東京文化会館がオープンした時、同じような批判があったことを思い出します。当時は新聞にまで取りあげられました。昭和37年のオープン当時のメインの会場は日比谷公会堂と産経ホールでした。文化会館の響きはこれらのホールと比べると異常に長かったからです。しかし、現在はどうでしょう。文化会館大ホールの響きは都内のオーケストラからは標準的な響きとして評価されています。
楽団や演奏家の慣れの中にはホールを道具として使い込んでゆく工夫や努力もよい音、よい響きに変わってゆく大きな要因のように思います。現在のNHKホールでのN響ですが、パートの配置や舞台の構成を変えながら、よい響きを模索してこられた苦労話を事務局の方から聞きました。
先日、ある席でNHKホールのことに話が及んだ時、都内各楽団やホールの演奏サービスをされているN氏から、NHKホールではクラシックのコンサートにも拡声を行っているという話を聞きました。N氏の周りにはこの仕掛けを信じで疑わない人が結構いるようです。NHKホールもこのくらい響きが変わったということです。私も以前スピーカによる響きの補正を試みているという話を聞いたことがありますが、現在は何もしていないと信じています。もし、拡声を行っているとすれば、NHKのホールのPA技術は大変なレベルです。
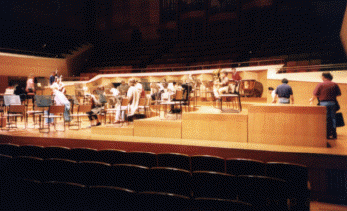
ところで、ホールを使い込む工夫は、サントリーホールでも行われています。6月15日のルジェロ・リッチと千住真理子による協奏曲の夕べをお聴きになった方は、日本フィルのステージが後ろにゆく程、従来になく上がっていたことにお気付きだと思います。各楽器のパートの高さ関係が響きのバランスに影響するであろうことは容易に想像できます。特に管と弦とのバランス、低弦の出方、一階席と二階席とのバランスなどは、わずかな高さ関係でかなり異なることをこのホールで体験しております。場合によっては、図-1のような迫り上げステージを試みることもあります。
以上のような、慣れとか使い込むという言棄で代表される要因以外に、ホール自体もなんらかの変化をする、という仮説も否定できないように思います。その理由として、最近、初めてサントリーホールで演奏する楽団で、オープン当初のようにハラハラする演奏がなくなったということ、またベルリンフィルというような由緒ある楽団のメンバーがオープニングの時と響きが変わったことを指摘しているということです。
いったい何がどう変化したのでしょうか?一般の話として聞くのが、コンクリートや舞台の床などの乾燥が影響してくるのではないかということ、もうひとつはホールの響きによって材料がエイジングされることです。ヴァイオリン工房のヴァイオリンと同じ原理です。
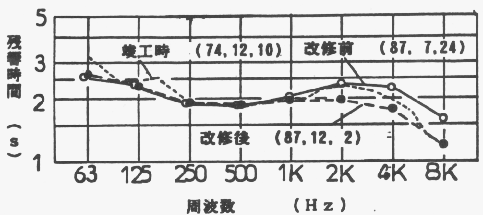
湿気の影響といえば、雨の日にコートや傘の持ち込みによって室内の湿度が上がり、それが、楽器、とくに弦楽器に影響することは考えられますが、コンクリートが乾いてくることによる影響は現在の技術ではちょっと説明できません。乾燥をふくむエイジングの効果が考えられるのは舞台の床ではないかと思っています。舞台の床はホールの内装面の中で楽器的な要素が一番大きい個所ではないでしょうか? また、荷重を受けるという点、消耗が激しいという点では舞台の床の他に客席の椅子があります。特に椅子の取り替えの影響は明らかです。図-2は昨年椅子を張り替えた上野学園石橋メモリアルホールの残響時間を前の状態と比較した結果です。石橋メモリアルホール独特の響きのくせが緩和されたことは事実です。ピアニストの松浦豊明氏はこの響きの変化をただちに指摘されました。松浦さんは現在の響きのほうを好まれています。
ホールの響きの変化というのは不思議な現象です。ただし、幸なことに“変化は必ずよい方向に向かう”という事実です。ご意見があれば是非お聞かせ下さい。
スピーカの指向性論争in USA
5月の初旬AES(Audio Engineering Society)の第6回のコンベンションがNashvilleで、中旬にはNSCA(National Sound and Communications Association)Expo’88がRenoで開催されました。これと前後してElectro Voice、Bose社による見学会、講習会がアメリカと日本で開催されました。永田事務所からも、中村、浪花、稲生、小口の4名が参加、この機会を利用してメトロポリタンオペラハウスの電気音響設備の実態や電気音響設備を利用した音場可変方式の利用状況の調査などを行いました。面白い話題が多々ありますが、今月はまず、アメリカで大きな論争を呼んでいるスピーカの指向性と明瞭度の間題を取り上げてみました。
Altec社のA-7で代表される現在のホール用スピーカシステムがわが国のホールに登場しはじめたのは、昭和40年にはいってからです。このシステムは当時の主流であったトーンゾイレといわれるコーン型スピーカを縦に配列したシステムに比べると、大出力に耐えるということ以外に、残響のあるホールでも明瞭度がよい拡声ができるということが大きな魅力で、あっという間にホール用スピーカとして定着しました。ところで、このシステムの設計手法を体系化した技術者にDon Davis氏がいます。PAG-MAGという評価法をもとにしたスピーカシステム構成の設計法など、残響時間の設計法に匹敵するともいえる成果だと思っています。彼がこのたびElectro Voice社の招きで、彼の著書“Sound System Engineering”の改訂版を教科書として2日間の講習会を山中湖畔のホテルで開催しました。ホールの現場から生まれた彼の話はこれまでの講習会にない新鮮さがあったようで、内容も充実しており、出席の浪花、小口の二人は感動していました。
一方、10年くらいになるでしょうか、Bose社の802、901というユニークな小型スピーカが登場し、展示場、宴会場、イベントホールなどを足場として急速に浸透してきていることもご存じのことと思います。Dr.BoseはMIT(マサチューセッツ工科大学)の現役の教授で、会杜は研究開発に力をいれており、わが国で想像していたイメージとは大違いです。BOSEの本社はボストンの郊外の丘の上にあり、工場というよりも“institute”といった方がふさわしい施設です。
ところで3年前になりますが、同社研究者のJacob氏からAES誌にスピーカの指向性と明瞭度に関する一連の実験をもとにした論文が提出されました。(J.Audio Eng.Soc.,33(1985),950)その内容はスピーカの指向性を表すQと子音明瞭度損失Alconsが反比例するというKleinの式への反論でした。しかし、その結果が拡張され、スピーカの指向性は明瞭度に関係しない、とまで言いきったために、Davis氏の考え方と対立することとなったのです。今回の2社の講習会でもその対立が浮かびあがったようです。
響きの長い空間で音源からの距離が遠い場合、直接音成分のエネルギーを集中させ、残響音エネルギーの増加をふせぐためにも、スピーカの指向性は必要です。ただし、ある条件では無指向性に近い特性のスピーカでも十分な場合もあります。また、拡声のシステムではハウリングという現象があり、これをさけるためにもスピーカの指向性制御は必要です。ハウリングで拡声レベルが制約されると、当然実効的に明瞭度は低下します。
5月19日、昭和女子大人見記念講堂でベリオの“シンフォニア”という8人のシンガーの歌を拡声するという珍しい曲がありましたが、その際Boseのスピーカがステージ上に置かれ、声の拡声に使用されました。声の内容が明瞭に判別できるのは前から10数席程度の範囲でした。一方、数年前旧国技館での実験ですが、ホーン型スピーカよりもコーン型のスピーカの方が拡声できる範囲が広かったという経験もしています。Jacob氏の実験は正しいのですが、指向性の必要性を否定するには実験条件が不足しています。
拡声設備の明瞭度というのは様々な条件に左右されます。わが国のホールはその大きさからも、ライブさからも明瞭度についてあまり気を遣わなくてもよかったことは事実です。しかし、今後の大型のイベント空間やコンサートホールでは明瞭度についてかなりシビアーな設計が必要になることは事実です。それにわが国では形、大きさの制約もあります。指向性は依然として拡声設備の大きな課題であることは変わりません。
NEWSアラカルト
富田義男氏“音を探ねて”、『JAS Journal』6月号より
戦前のNHKの建築音響技術の紹介です。昭和12年、当時は日本放送協会であったNHKに大阪放送会館が、引き続いて昭和14年に東京放送会館が開館しました。当時音響設計を担当されたのがNHK技研の大先輩、現在ソニー顧問の島茂雄氏で、各スタジオの最適残響特性の検討、残響時間の設計などの詳細が、同じく先輩の富田義男氏の『JAS Journal』6月号の記事で紹介されました。私などはじめて知った先輩の仕事です。なお、富田先輩の“音を探ねて”は今月で13回という力作で、敬朊せざるをえません。先人の歩みを知る上で参考になります。
千秋晴三氏“造形と音響(1)―野外劇場―”、『建築界』5月号より
同じくNHKの先輩の千秋晴三氏の建築と音響の歴史についてのシリーズが『建築界』5月号の野外劇場から始まっています。千秋氏はNHKの建築部のご出身で、牧田先生らと一緒にお仕事をされた仲間のお一人です。たいへんな勉強家、読書家であることが密度の高い記事からうかがえます。劇場と音のルーツを探ねるこのような記事、期待しています。
石堂淑郎氏“君は聞いたか廃墟のフルトヴェングラーを”、『新潮45』7月号より
副題として“音楽で感動するということはどういうことか?相次いで来日する世界一流のオペラ、音響効果を誇る豪華なホール、ハイテクを駆使したCDの音色……いずれも音楽の感動とは無縁のものである。”
この副題に氏のいわんすることは言い尽くされています。私の秘蔵版のディヌ・リパッティのブザンソンリサイタルの記事にひきずられて読みました。現在のギラギラした音楽ブームに対しての痛烈な批判です。