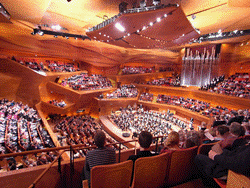
コンサートホールのステージ音響 ―Danish Radioの場合―
去る1月20日、デンマーク国立放送局の新コンサートホール(Danish Radio (DR) Concert Hall)がオープンしてちょうど5年を迎えた(オープンの際の記事:本ニュース255号2009年3月)。5周年を記念した特別のコンサートというわけではなかったが、通常のコンサートの後で関係者が集まってレセプションが開かれ、それに招待を受けて参加してきた。放送局に所属するオーケストラ(Danish Radio Symphony Orchestra)がレジデント・オーケストラとして、そのリハーサルとコンサートの全てをこのホールで行っている。日本でいえばN響とNHKホールのような関係であろうか。ただし、NHKホールは残念ながらクラシック専用のコンサートホールという訳ではなく、またN響も普段のリハーサルは別の専用練習場にて行っているという点で、Danish Radioの場合とは大きく異なっている。
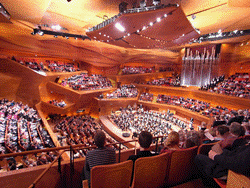
DRコンサートホールは、ベルリン・フィルハーモニーのような、いわゆるヴィニヤード方式の客席形状が採用されたコンサートホール(約1800席)である。客席がステージの回りを取り囲む形で配置されており、日本のホールでいうと東京のサントリーホール、札幌コンサートホール(Kitara)、ミューザ川崎シンフォニーホール等のレイアウトに近い。DRのステージ回りで音響に関連して特徴的なこととしては、弦楽器セクションまで含めた電動のオーケストラ・ライザー(舞台ヒナ壇迫り昇降装置)とステージ上部に吊り下げられた音響反射板がある。この音響反射板は上下昇降機構を備えており、高さを自由に変更可能である。もっともこの昇降機構は、音響反射板に組み込まれたステージ照明器具やマイク吊り装置、その他諸々の吊り装置の調整や保守点検のために設けられたものであり、音響調整のために導入されたものではない。音響的には設計時点で設定した高さがあり、それを大きく変更することは想定していない。高さを変更するとしても、微調整を行う程度に使えればよいという程度の想定であった。
動くとなると動かしてみたくなるのが人の常である。オーケストラのメンバーの中でも特に好奇心を持った人達は是非動かしてみたいというということになり、上部の音響反射板、オーケストラ・ライザーの両方について、積極的に動かして調整が試みられることになった。DR側、オーケストラ側もさして大事とは考えないで気軽に動かしてみたかったようである。音響設計を担当した我々の方に知らされたのは、色々な試みが実施された後のことであった。結果として、オーケストラのメンバーは混乱に陥ってしまったのである。上部の音響反射板についても、ステージ床のヒナ壇迫りについても、その評価については全くバラバラで、ある奏者は高い方が良いといい、他の奏者達は低い方が良いというなど、オーケストラ全体にとって一定の良い方向を見いだすことはできなかった。指揮者による評価も人によってマチマチで、一定の評価結果を得るには至らず、混乱を極める状況となってしまったのである。

オーケストラ ヒナ壇迫り
一般にステージ上の音響の評価、特にオーケストラを対象とした場合は非常に複雑なものとなる。楽器の種類も様々であり、またステージ上のオーケストラ内における各奏者の位置も全く異なる。演奏する音楽も様々であり、指揮者が誰かによって結果が異なることもよく経験する。そして、ステージ上の音響の評価はこれら複雑な条件下にあるステージ上の奏者の主観を通してのものになるという事である。さらに事が複雑になる要因として「慣れ」の問題がある。全く同じ状況であっても、演奏者が慣れてくることによって、すなわち時間の経過によって、その評価結果が違ってくるのである。よく「ステージ上のベストな音響」などと一言で言い表されるステージ音響も、全くケース・バイ・ケースといっていい程、違うのである。ウィーン・フィルのホール(ムジークフェラインスザール)とベルリン・フィルのホール(フィルハーモニーホール)では、そのステージ上の音響特性は全く異なるにも拘わらず、各々のオーケストラにとっては各々のホールが最高に演奏し易いと評価される。DRオーケストラからその混乱状況の連絡を受けてから直ぐに、あらゆる試みで動かすことを止めることと、天井反射板を設計当初の位置に戻して固定すること。最低でも1年間はこの状態を堅持して動かさないことを進言した。その状態で十分時間を掛けて「慣れ」てから、必要に応じてゆっくり調整していく事が、ステージ上の音響を考える上で必要かつ重要なプロセスと考えたからである。
今回の5年目の記念演奏会は、過去の混乱の時期を経た後、ステージ回りの音響上の可動要因を一旦固定して相当期間の時間を経た後のことである。コンサート後にオーケストラのメンバーやDR放送局側のスタッフと有意義なミーティングを持つことができた。音響可動部分に関する一時期の混乱はほぼ収まり、オーケストラもかなり落ち着いてきた状況だという。音響設計側としては、今後は必要に応じて音響可動部分を動かすことによって可能な音響調整についてゆっくり相談していけばよいと考えている。(豊田泰久記)
デュッセルドルフ・トーンハレ
ドイツ国内で日本人が最も多く住む街として知られているデュッセルドルフ市に、音響的にたいへん興味深いホールがある。それは、デュッセルドルフ交響楽団の本拠地、デュッセルドルフ・トーンハレである。
同ホールの歴史は1926年に遡る。もともとプラネタリウムとして建設され、戦後、戦争で破壊された部分を修復して多目的に使用されるようになり、1970年代にやはり戦争で破壊された旧トーンハレの代替として、ドームのイメージはそのままでステージ上部に大型音響反射板を設置してコンサートホールとする内部改築が行われた。さらに2005年、耐火とアスベスト除去を目的とした大規模改修が行われた。実はこのとき、ドーム形状に起因する室内音響的な懸案事項も解消された。

本ニュース149号(2000年5月)でも、凹面で構成される空間内ではどこかに必ず音の集中する場所が生じることを紹介した。円筒と半球面(半径約20m)で構成されたデュッセルドルフ・トーンハレはまさにその典型で、2005年改修の前のトーンハレでは、“ドアをノックする幽霊(Klopfgeist)”と名付けられた木製ドーム面からの反射音が集中するエリアが存在していた。2005年改修の音響設計を担当したオランダ・Peutz社Vercammen氏のレポートによると、そのエリアでは直接音より約110ms遅れてドームから集中的に反射音が到来し、ETC(エネルギー・時間・カーブ)表示で直接音より14dB大きな集中した反射音が観測されている。
本ニュース149号では、音の集中を“緩和”する方法として、(1)円形を部分的に崩すこと、(2)円形あるいは球形部分を散乱・吸音仕上げとすること、の2つを上げている。2005年改修で採用された音響集中解消策は、屋根ドームはそのままで内装ドームを取り外して新たな天井を設け、その内側に音響的に“透明”なドームのイメージを残すというものであった。新たな天井面は、屋根ドームの内側という制約のもとに、そこに入射した音を真下あるいは新たな天井の別の部位に反射させるような(redirect)、すなわち音の集中を起こす方向には反射させないような形状とし、音響模型実験によりその効果が確認されている。新しい天井は、ドーナツリング状の水平面と、音の波長と同程度の大きさのジグザグの立ち上がり面で構成されており、上記緩和策の両方が実行されたとみることができる。
しばらく前このトーンハレを訪れる機会を得た。なるほど、視覚的なイメージはドームである。ただし、ドーム面は音響的に透明な金属ワイヤーメッシュで構成されており、その裏側の天井面を照らす青い光が複雑に反射して、幻想的な雰囲気を醸し出している。ワイヤーメッシュは客席背後の平筒壁まで下降してきており、そこに近づくと裏側の複雑に折れた反射面を視認できる。また、メッシュを支える下地材には丸パイプを使用し、ステージを向くバルコニー手すり壁には音を散らす方向にガラスの切片が並べられるなど、徹底してドーム中心を向く面を少なくする工夫が施されている。


あるオーケストラのリハーサル時に様々な席でホールの響きを聴くことができた。打楽器のような短音でも、音が集中するような印象はほとんどなく2005年改修が大成功であることを、身を持って確認することができた。また視覚的にドームに見える空間で、音響的な特異現象である音の集中をほぼ感じないまでに解消するのに必要な処理の良い説明資料が得られた。(小口恵司記)
デジタル音響機器の開発者、栗山譲二氏を囲んで
先月は、舞台音響設備のデジタル化の第一人者である栗山譲二氏を講師として事務所へお招きし、これまで関わってこられた仕事についてお話しいただいた。本ニュース35号(1990年11月)でも取り上げた、ウィーン国立歌劇場の世界初のフルデジタル音響調整卓を開発した方で、ご存じの方も多いのではないだろうか。
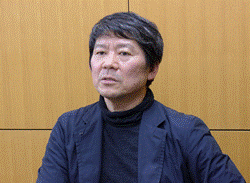
学生の頃からデジタルミキサーを作りたいと考えていた栗山氏はTOA株式会社に入社し、まずは電話交換システムの部署で電子工学を学ぶ。その後デジタルシグナルプロセッサー(DSP)の開発に従事し、入社後10年も経たない1989年には、今なお人気の高いサウンドDSP「SAORI」を完成させている。
栗山氏がSAORIの開発をしている頃、ウィーンでは国立歌劇場のトーンマイスターのフリッツ氏が、音響設備を一新し、全てをデジタルミキサーで制御できるようにしたいと考えていて、TOAの社長らとの会食の際にその構想を話したそうである。それを聞いたTOAの社長はSAORIのことを思い出され、まだまだ若い栗山氏にすぐに尋ねる。「デジタルミキサーとは何か、そういうものは作れるのか。」栗山氏は説明後「作れます」と答え、すぐに単身でウィーンへ飛ぶ。この時点では他にも候補がおり、業務請負は確定ではなかったと言う。ところがフリッツ氏のいる国立歌劇場の音響調整室に案内され、そこにたまたま開いて置いてあったオペラ「魔笛」のスコアを読みながら、手書きしてある印の意味をフリッツ氏に尋ねたところ、他の候補のエンジニアにはスコアの読める人はいなかったために、一気に打ち解けたそうだ。栗山氏は大学時代の講義のおかげでスコアを読めたと言うが、それからフリッツ氏と仲良くなり、信頼され、開発を請け負うことが決定している。
開発期間はたった2年と限られた中で、これまでアナログだったものをゼロからデジタルシステムとして構築しなければならない。そんな中あくまでも「全デジタル化」にこだわる栗山氏とフリッツ氏は、議論を重ね細部までこだわり、完成度の高いものを作り上げた。例えばホールは騒音が非常に小さいので、スピーカ出力がない間にはアンプからの残留雑音が出ないように外部リレー制御機能を付加したり、今でこそ当たり前のタッチパネルディスプレイも、四半世紀程前のこの時すでに導入されていたりする。名称も時代を先取りし、iミキサーを省略した「ix」とされていて、その先見性に感服する。
偶然が重なって舞い込んできたチャンスをつかみ、夢を叶えた。絶対に妥協しないことで、テクノロジーの進歩にも飲まれない製品ができる。そう語る栗山氏は今も本気で好きなことを追い求める熱意にあふれていて、聞いている私も胸が熱くなった。最近特に時間や経済的な制約が厳しい建築業界でも、資材を無駄にせず、長く使われるものを造るようにしなければならないと感じている。(鈴木航輔記)