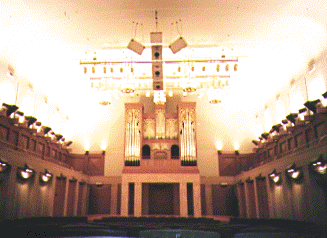
動機が問題
3 月9 日(日)BS放送の批評提言で、京都大学の林春男教授が一昨年の阪神淡路大震災の現地における一部のマスコミの取材の姿勢について批判されていた。その要旨は現地の実態を伝えるということではなく、あらかじめ用意してきた筋書にそって都合のよい情報を掻き集め報道するという姿勢である。本Newsの2月号で、能舞台床下の瓶(カメ)のようなものが、あるコンサートホールに設置されており、これが良い音響効果の秘密であるかのような趣旨の放送があったことを豊田が指摘したが、マスコミの報道にはこの種の記事は意外と多い。マスコミだけではない。3月に行われた音響学会に春季研究発表会においても、出発点、動機に疑問のあるテーマが幾つかあった。問題は何をどのような視点から取り上げるか、その動機、出発点の姿勢に対してのチェックが案外なおざりにされているように思う。
モーツァルトの音楽のように天からの啓示としかいいようのない動機によって生まれた作品もあるが、われわれ凡人の動機には問題が多い。研究という分野に限っても、固定概念に執着したテーマ、流行を意識したテーマ、事前の調査が不十分で独り善がりのテーマ無理に現場と関連つけたテーマなどを感じることがある。
信号処理の手法の一つとして、同期加算という方法がある。これを用いることによって雑音の中に隠れている信号を取り出すことができる。また、統計的手法によって、複雑な現象のなかに潜む複数の軸を抽出することもできる。このような客観的な手法も開発されてはいるが、現実問題としては、冒頭の取材の姿勢のように、結果を意識しすぎて、実験では大きく外れたデータを、調査では都合の悪いデータを切り捨てるようなことも行われている。体系を創り上げる上では仕方がないとしても、これによって、雑然とした資料の中に潜む真実を切り捨ててしまう可能性がある。音響効果のような複雑な現象に対しては一つの理論や主張をおしつけることは危険である。アメリカの音響学者Beranek は最近の著書において、独立した(?)幾つかのパラメターを使って、コンサートホールの音響効果をランク付けするという大胆な評価手法を紹介しているが、彼の評価にはボストンやウイーンで代表されるシューボックス型ホールの響きへの執着があるように思う。いまや、コンサートホールはシューボックス型の枠にとどまる時代では無い。音響界の大御所として新しいホールを見通した評価の展望が欲しかった。
われわれが演奏会の現場で体験する音響効果、そこには音楽のジャンル、演奏の規模や内容、聴取場所、個人の嗜好など様々な要素が絡んでおり、これらを別にしては捉えることはできない側面をもっている。楽器であるだけに、弾き手と曲目によっては今まで知らなかった効果の発見もあり、また、音の教科書では決して推奨されることのない最前列の席の響きに感動することもある。今後の評価研究は実験室では切り捨ててきた以上のようなファクターをふまえたアプローチが必要である。それには虚心坦懐に現場の響きに心を傾け、その中にテーマを見出だす姿勢が必要ではないだろうか。(永田 穂記)
オペラに電気音響の補強が必要か
ご存じの方も多いと思うが、3月20日付けの朝日新聞朝刊に約半頁の紙面を割いて“「生こそ」のオペラ、こっそり電気の音?”という記事が掲載された。この記事の要旨は、クラシックコンサートやオペラは生の音が常識だが、最近のデジタル技術の進展によって客に気付かれないように拡声する技術が進んでいる。これは時代の必然なのか、聴衆への裏切りなのか?……というものである。記事の内容は筆者が知る情報とほとんど同じであり事実だと思う。この問題は、筆者らが参画した新国立劇場の舞台音響設備の計画・設計の過程で、建設委員会において長期間にわたって論議の対象になり、この間、関わった経緯があるだけに興味深く読んだ。
クラシックコンサートやオペラは、その長い歴史の中で伝承され育まれてきた芸術だから当然のことながら生の音が前提であり、それゆえに専用のホールや劇場の一聴衆となってはじめてその良さを味うことができる。聴衆のほとんどがこの感動を味わいたくて、つまり生の音が当たり前のこととしてコンサートホールやオペラ劇場に足を運ぶのであるから、聴衆の知らないところで電気的に補強することは聴衆を欺くことになり姑息なやり方といわざるを得ない。もし、自分が聴衆の立場であればとても容認できることではない。ただし、聴衆にチケット購入前に事前に周知されているとか、クラシックでも明らかに音響設備を使用しないとコンサートが成り立たないことがだれにも分かっているような場合は別である。ドームでの三大テノールのイベントを生の音で聴けると思う聴衆は一人もいないだろう。
音の好みは個人差があるので、電気音響で補強することにこだわらない人がいるだろうし、また、生の音に対するこだわりは時代とともに少なくなっていくのかもしれない。しかし、だからといって電気音響で補強することが本当に聴衆のためになるのだろうか。電気音響に頼る前に、声量のある歌手に変えるなどを考えるべきだし、それでもやるというなら事前に聴衆に知らせて堂々とやるべきであろう。電気音響設備の性能が年々高くなり生の音との違いが分からないようにコントロールすることが可能になってくることは必然であり、それだけにこの技術の使い方には十分な配慮とコンセンサスが必要だと思う。今のような使い方を続けていると、いずれ聴衆のホール離れという代償を払わなくてはならない時が来ないかと危惧する。
ところで、生の音で上演されるのなら電気音響設備はいらないか、というとこれはまた別の問題である。欧米のオペラ劇場では、客席から見えないようにスピーカが埋め込まれ音響調整室には最新機器が設置されている。これらの設備は、なにも歌手の補強用ではなく、その主な役割は効果音の再生である。効果音は昔は擬音発生器を操作していたが、今は電気音響設備に変わっている。擬音発生器による音自体が人工音であるから効果音の再生に電気音響設備を使用することは聴衆を騙すことにはならないし、聴衆の反発もない。なによりも電気音響設備の方が迫力のあるリアリティの高い音が出せるし、操作ミスも少ない。コンサートホールにも電気音響設備は必要である。もちろん演奏中は不要だが、場内アナウンスやトークコンサートのスピーチの拡声になくてはならない。 しかし、生音のこだわりを理由にしばしば電気音響設備不要論や、不要ではないにしても小型スピーカに質素な機器でよいという考え方にすり替えられる。この考え方はいかにも説得力がありそうだが短絡的思考というべきで現実的ではない。なぜなら効果音で雷の音をリアルに再生するとなるとかなり大型のスピーカと大出力のアンプが必要だし、コンサートホールにしても響きの多い空間でスピーチの明瞭度を確保するためには多目的ホールより多数のスピーカが必要なこともあるからである。演出や音楽関係者、建築家などに上述のような主張をされる方が意外に多いこと、そしてこのような方々に、コンサートホールやオペラ劇場といえどもそれ相当の電気音響設備が必要であることを理解してもらうのが大変であることを業務を通して知った。前述の新国立劇場の計画における議論の論点ももっぱらこの点であった。
この記事を契機に思うことは、オペラの電気的な補強の例のように、目先のことだけで行われていることや様々な立場からの視野の狭い主張が、本当にこの世界の将来を考えたものであるかを再考する必要があるということである。(中村秀夫記)
カザルスホールにパイプオルガン設置
昨年10月のニュースでも紹介したように、カザルスホールでは開館10周年に向けてパイプオルガンの設置工事が進められていたのだが、昨年の10月にはオルガン台が、そしてこの3月にようやく本体のパイプオルガンが設置された。写真のように、今まで白い大きな壁だった舞台正面がパイプオルガンによって華麗に変身した。パイプオルガンは、ドイツのユルゲン・アーレント氏製作によるもので、41ストップ、3段鍵盤である。
調整が終わったばかりの3月19日、アーレント氏の友人であるイタリアのオルガニスト、ロレンツォ・ギエルミ氏の演奏による内々のコンサートが催された。パイプオルガンの音は装飾と同様に繊細で美しく、そして優しくホールに響き渡った。ただ、オルガニストの演奏にもよると思うが、個人的にはもう少し重厚さが欲しいという感じがした。
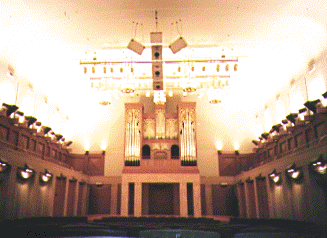
カザルスホール10周年記念フェスティバルの初日である10月10日、ウォルフガング・ツェラー氏の演奏によるオルガン・プレミエコンサートによって、オルガン開きが行われる設計段階から計画されていたパイプオルガンが設置されたことによって、ようやくカザルスホールが「完成」した。(福地智子記)
音響学会春期発表会とASVA
昨年から今年にかけて、音響関連の学会の記念大会・行事が続いた。今年の音響学会春季発表会は関西支部創立60周年を記念して、3/17~19に同志社大学・新田辺キャンパスで開催された。室内音響分野では”音場の評価と設計”と題したスペシャルセッションが組まれ、ホール音場の予測、物理指標、音場支援などに関するレビューと研究発表が行われた。当社はポスターセッションで、ナディアパーク、富山市芸術文化ホール、長岡リリックホール、クィーンズランド音楽院の作品紹介を行った。続く4月2日~4日に音響学会創立60周年および騒音制御工学会創立20周年を記念して、”International Symposium on Simulation, Visualization and Auralization for Acoustic Research and Education”-ASVA97が早稲田大学の国際会議場で開催された。コンピュータによる音や振動の可視化、可聴化を駆使した講演とポスター発表が行われ、プレゼンテーションの方法で参考になる点が非常に多かった。当社はホールの室内音響設計で利用しているコンピュータシミュレーション、光学模型実験および音響模型実験の特徴と適用限界について、最近のプロジェクトからディズニーコンサートホール、京都コンサートホール、札幌コンサートホールを例にポスターと模型実験の音で紹介した。
昨年末のジョイントミーティング(ハワイ)からこれまで、ホール音場のモデル化手法の動向を網羅的に見ることができた。コンピュータシミュレーションでは、幾何音響では取扱いの難しい音の散乱、回折、座席面の取扱いなどを積み残したまま、計算されたインパルス応答にドライソース(録音室の響きを含まない音楽・音声)を畳込んで聴くことができる可聴化技術が広く実用化されている。最近は、波動性を考慮したより正確なインパルス応答の予測を目指して、音の方程式を近似的に解く研究が盛んになっている。音響模型実験では、ディジタル信号処理により1/10より小さなスケールの模型でも、高品質なインパルス応答の測定が可能となり、やはり畳込まれた音楽を聴くことができる。こうしたモデル化手法で得られた音を聴いて、新しいホールの音の響きの絶対的な評価ができるかというと、それは難しい。実際のホールのステージに置かれた無指向性スピーカからドライソースを再生してダミーヘッドを介して録音し、持ち帰って再生してみてそのホールの評価ができるであろうか?
これらを通して、予測でも評価でも今後ますます詳細な内容に入って行きそうな研究と我々の実務とのギャップを強く感じた。タイミングよく音響学会誌4月号では、”室内音響設計の現状と課題”と題する小特集が組まれている。その冒頭で、石井聖光・東大名誉教授が、”室内音響設計には学術レベルの研究のほかに、実務レベルとの橋渡しが必要な研究が必要である。”と述べておられる。(小口恵司記)