
旧NHKホール(内幸町)
戦後50年を迎えた今年、一つの区切りとしていろいろな事が掘り返され、また語られている。ここに、<私の中のホール>として、昭和30年という戦後の復興期に誕生し、昭和48年という高度成長期のとば口で消えてしまった一つのホールを紹介したい。今はなき旧NHK ホールである。われわれの年代の方だったら、このホールをご存じであろう。「二十の扉」「ジェスチァー」「向こう三軒両隣り」など昭和30年代のテレビの人気番組の舞台となったNHK の公開番組ホールである。

筆者がNHK に採用になり、ローカル局での実習を終え、世田谷の技術研究所に配属されたのが1949年の10月である。まだ、戦後の混乱、貧しさはいたる所にあった。しかし、それまで経験できなかった自由が広がっていった時代である。明るく、健康的な時代であった。そのような時代にこのプロジェクトは開始された。
当時のコンサート会場といえば、まずは日比谷公会堂、それに、共立講堂くらいであったと思う。筆者がカラヤン率いるベルリンフィルを聴いたのも日比谷公会堂であった。
新しいホールの音響設計は技術研究所第一部の音響効果研究室が担当する事となった。チームが結成されたのがたしか1951年である。当時、部長は戦前から戦中にかけて多くのスタジオを手掛けてこられた故島茂雄氏、室長は故中島博美氏、実務のチーフが大阪大学から来られた牧田康雄氏であった。
公開番組用ホールという形式の空間はNHK でも初めての試みであり、音響設計の資料といえば、限られた吸音材の吸音率資料くらいしかなかった。1960年にオープンしたロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールの資料を上司のデスクで見たような気もする。設計は牧田主任の指導のもとに、反射音線図による室形、主として天井形状の設計と、内装材の吸音率の測定が、急遽造られた容積約 50m3の小型の残響室で開始された。
舞台上の音源といくつかのマイクロホン位置について反射音の遅れ時間、壁、および天井面での音の入射点が手作業で行われた。その結果は牧田先生の著書「建築音響1に詳細な記述がある。当時、室内音響設計の根底にあった考えは直接音到来後50msまでの初期反射音が有効だとする、Haasの実験結果であり、牧田主任の指導も50msまでの反射音に着目し、直接音とこの初期反射音とのエネルギー和を客席内でできるだけ均等にするという方針で行われた。したがって、利用できる反射面は天井面であり、側壁からの反射はエコーになるとして拡散体を設置する、といった牧田流の整然とした方針であった。拡散体についても、当時、ラジオスタジオで盛んに使用されていたポリシリンダー(蒲鉾上の散乱体)の散乱効果の理論解析結果(伊達玄氏による)から山間隔と高さが決定された。しかし、今日話題の側方反射音の効果はまだ知られていなかった。
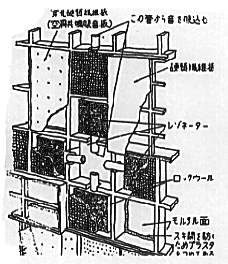
当時はまだグラスウールはなく、断熱材のロックウール縮整形した繊維板が吸音ボードの主流であったように思う。もちろん、プラスターボードは当時も広く使用されていた。この建築材料の吸音率測定を担当されたのが故坂本吉弘氏である。また、共鳴吸収を利用する有効板を用いた吸音構造も、理論的なアプローチとともに、有孔率、背後空気層の厚さなどをかえた各種の構造の資料が集積され、残響時間の設計の基盤が整備されていった。
また、筆者は牧田主任の指導のもとに、ヘルムホルツレゾネーターによる吸音の研究を担当していたが、その結果もこのホールの吸音構造の一つとして用いられた。すなわち、後壁からの反射音を減衰する目的で、共鳴周波数50Hzから100Hz 間で合計158 個のレゾネーターを製作し、これを図のように後壁に埋込んで使用した。さらに、天井の隅には残響調整用として、レゾネーターを天井裏から挿入できるように、ネックを差し込む蓋付の開口が設けられた。残響の調整にしてもこのような慎重な対応が行われたのである。
舞台周辺はモザイクタイル張りの剛な拡散構造であり、舞台から後壁にかけて、順次吸音力が増してゆくように側壁の反射、吸音構造を配置した。なお、残響時間の設計は75Hzの低音域から行った。
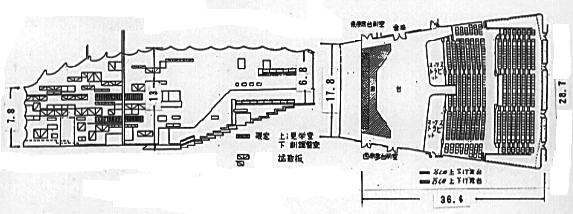
新放送会館の建築設計は山下寿郎設計事務所、施工は大林組である。ホールの設計を担当されたのは山下寿郎設計事務所の池田宏氏で、建築と音響の狭間で苦労された方である。断面図、平面図を示す。
図が示すようにこのホールはゆるく開いた台形の平面をもつワンフロアーのホールである。計画段階ではこのホールはコンサートホールとして出発し、舞台後部にはオルガンスペースも設けられていた。しかし、テレビ放送の構想が固まってくるとともに、テレビスタジオへの対応が進められる。もっとも顕著だったのは630 席の客席規模のホールとしては異常に大きい346m2という広い舞台である。この舞台には図からも明らかなように、舞台先端中央にはテレビカメラの引きのためのエプロンが設けられた。また、舞台奥には油圧駆動の2 段の迫りが設けられ、それぞれ75cm、25cmにセットできるようになっていた。当時のホールとしては斬新な機構であった。
オープン当時の残響時間の測定結果を右図に示す。室容積8,700m3にたいして、中音域で1.5 秒をこえるこのホールの響きは当時のホールとして画期的な響きであった。今考えると、ウイーンの楽友協会で体験したあのgolden rush ともいえる輝いた響きであった。それに、このホールのオープン前後から海外の楽団、演奏家の来日公演が始まるのである。カラヤン率いるベルリンフィル、ミュンヒンガー率いるシュットットガルト弦楽合奏団など、戦後の荒廃したわが国に、音楽の天使のようにやってきた演奏家、楽団の殆どの演奏がこのステージから電波となって各家庭に届けられた。
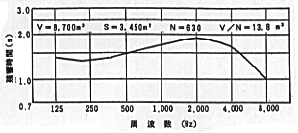
本ホールのオープンをまたずにNHK はラジオ局からテレビ局へと大きく変容して行く。それとともに、舞台天井にはテレビスタジオ並みの照明器具が設置されるようになり、コンサートホールとして出発したこのホールも視聴者参加のショウ番組用のホールとして知られるようになった。そして、NHK の渋谷の新放送会館への移転にともない、内幸町の放送会館とともに姿を消した。1973年7 月25日が最後の演奏会であった。18年という建築物としてはあまりにも短い命であった。
戦後このホールとあい前後して誕生したコンサートホールとして、横浜市紅葉山の神奈川県立音楽堂がある。前川国男氏設計になるこのホールは戦後の名建築の一つとして、建築界で保存運動が起こっている。一方、戦後のあの混乱の時期、全国のファンに音楽の感動を呼び起こしたこのNHK ホールの功績はコンサートホール本来の使命を考えると忘れてはならない存在というべきではないだろうか。しかし、ホールの響きを保存する術はない。このNHK ホールの響きは筆者が知る限り、NHK 交響楽団の活動を記録したLPレコード集2の中に3 曲入っているだけである。しかし、このようなレコードという形からではこのホールの響きの特色を知ることはできない。音の記録はまだ可能であるとしても、響きの記録は個人の思い出の中にしか残すこと以外にできないのではないだろうか。
なお、本文作成にあたっては、池田宏さんからお借りした国際建築特集「日本放送教会放送会館新刊」vol.22 No.6 June 1955, および、放送技術「放送会館新刊竣工特集] 1955年7 月号を参照し、また、図の一部を転載した。
このNHK ホールに関しては下記の図書に記述がある。(永田 穂 記)
- 永田穂:建築の音響設計 114 ページ NHK ホール 昭和49年11月 オーム社
- 永田穂:静けさよい音よい響き 190ページ 二つのNHK ホール 昭和61年8 月 彰国社
- 牧田康雄:建築音響 第5 章 音響設計 昭和35年3 月 日本放送出版協会発行 ↩︎
- The NHK SYMPHONY ORCHESTRA Live Recording since 1926 NO.2 No.3 NHK交響楽団 ↩︎
本の紹介
今月は下記の著書について、オルガン製作者の須藤宏さんからいただいた紹介原稿をそのまま掲載します。
『南蛮音楽 その光と影』─ザビエルが伝えた祈りの歌─ 竹井成美 著 音楽の友社 2300円
本書の著者は大分中世音楽研究会を主宰する研究者であり、国立宮崎大学で後進の指導にあたる教育者でもある。著者は学生時代に皆川達夫氏の元で隠れキリシタンの音楽の調査をする。それが彼女のその後を左右することとなる。従来、西洋音楽は明治時代に始まると一般には考えられてきた。が、そのはるか以前、安土桃山時代にすでに西洋音楽は我が国に伝わっていた。それだけではなく、オルガンも伝わっていた。日本でのオルガン製作もすでにおこなわれていたと言う。それらは全てキリスト教との関わりにおいてである。キリシタン大名の命題としてローマ教皇に派遣された遣欧少年使節がエヴォラの大聖堂でオルガンを弾いたという史実、現在では推測する他には方法がないのではあるが、マドリッドではヴィクトリアを、ローマではパレストリーナを、ヴェネツィアではガブリエルをこの少年達が耳にしたであろうことに著者は想いをはせるのである。何と夢多い話しであろう。ザビエルが伝えた祈りの歌を始まりとして、イエズス会の司祭教教育の一環としての音楽教育の方法とその成果、遣欧使節がいかに西洋音楽を身につけていたかが、多くの史料(その大多数は宣教師が国外に送った報告書など)をもとに記述されている。
実に出発以来8年と5ケ月の苦労の旅の後の帰国が待っていたのは禁教令であった。彼らが持ち帰った音楽、印刷術はキリスト教とともにことごとく歴史から消えてしまったように見えた。しかし、想像を絶する迫害の時を経て、ザビエルが伝えた音楽は歌い続けられていた。ここからは著者自身の生月島での調査研究が中心になる。隠れキリシタンが受け継いできた年中行事とそこで歌われる『歌おらっしょ』( 「おらっしょ」はラテン語の ’ORATIO’オラティオ「祈り」がなまったもの)についての記述は興味をそそられる。『歌おらっしょ』には属さないが、「さん・じゅあん様の歌」と「だんじく様の歌」を録音で聞く機会があった。隠れキリシタンの悲哀を歌って心を打つ。
日本にそれほど古くオルガンやオルガン製作が実在したということだけでもオルガン関係者にとっては興味を引くところであろう。この本の著者の話は理解しやすく、また常に人を引きつけるのである。この著書も同様に、わかり易く、それでいて全てのページに亘って興味を継続して読むことができる。おすすめの一冊である。(オルガン製作家 須藤 宏 記)
なお、本書にも関係のあるキリシタン時代の死者のためのミサ曲が聖グレゴリオの家で下記のように行われます。お問い合わせ:聖グレゴリオの家 Tel:0424-74-8915
11月5 日(日)14:00 死者の日の記念ミサ─サカラメンタ提要より
サカラメンタ提要:1605年長崎で印刷された典礼書 わが国最初の活字印刷楽譜