ヨーロッパのホール研修ツアー報告
永田事務所では1978年の夏、西ドイツ、オランダ、イギリスのホール、スタジオを訪ねるツアーを行った。ヨーロッパのホール、コンサートの印象は強烈であり、是非、再現したいという声は毎年あがっていたがなかなか果たせなかった。それがやっと実現する運びとなり、その第一陣として4月9日~16日の日程で入社2~3年目の女性社員3名と永田という顔ぶれでウイーン、ザルツブルグ中心のツアーを行った。
その1.ウイーン、ザルツブルグ、ミュンヘンのホール紀行
海外の著名なホールについては諸文献からの情報しか持たず、それらのホールの響きやコンサートの雰囲気を知らない─という若手組の実情を憂えた(?)永田社長の配慮から、その第1陣としてまずわれわれ新人が出発した。訪れたホール、コンサートは下記のとおりである。旅行は英・独会話両方を永田に頼るという有様であったが、予定した以外のコンサートも聴くことができ、皆、それなりに貴重な経験であったと思っている。
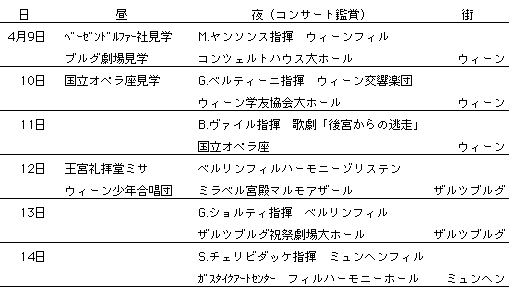
ベーゼンドルファー社見学: ベーゼンドルファー社のマネージャー、Hans Hartman氏の案内により、ウィーン市内とウィーンから約50km離れたNeustadtという静かな町にある二つの工房を訪ねた。ピアノ本体の製造が行われているのはNeustadtで、ここでは木材の保存から各パーツの製造、組み立てまでが(驚いたことに)全て手作業で行われている。市内の工房ではその出来上がったピアノの調律等、最後の仕上げ作業が行われる。またこの一角には、ベーゼンドルファー・ザールという小さなホールがある。その昔、乗馬学校の校舎を、音響が良いというのでコンサートホールとして使用するようになったのが始まりという。現在のホールは改築後のもので、小じんまりとした普通の住宅の一室を少し広くしたような部屋では、少し押さえられた響きがピアノの音に程よく合っていた。
コンツェルトハウス、コンサート: 筆者にとってはまさにヨーロッパでのコンサート初体験である。まず、ホワイエにてクロークが有料なのに驚く。ホール内に入ると、シューボックスというには幅広のホールは、広い平土間部分とそれを囲むバルコニーから、コンサートホールというより舞踏会場のような印象をうける。わくわくする気持ちとは裏腹に、不覚にも時差ボケによる眠気に襲われ、一同睡魔と戦いながらのウィーン・フィル鑑賞となる。席はPARTERRE(平土間席)。柔らかく優しい音に驚いたが、諸ガイドブックによると、このホールはかの楽友協会大ホールの響きに比べればシャープなのだと言う。自分の中の「響き」に対する基準が変わっていく快いカルチャーショックを覚えると同時に、翌日の楽友協会への期待がさらに増した。(横瀬鈴代 記)
国立オペラ座見学: 以前からこのNEWSに登場しているトーンマイスターのフリッツ氏、昨年の暮れからオペラの音響調整・効果の勉強で来ている日本人の山海僥太氏の取り計らいでオペラ座の見学ができた。私たちは劇場内を案内され、音響調整室でフリッツ氏の説明を聞いた。氏は劇場のスピーカの改造計画や新たなる調整卓(音像制御を目的とするらしい)の計画等も聞かせてくれた。オペラ演目そのものは古典かもしれぬが、オペラの公演自体は何時も新しいものを求めているらしいことが舞台裏の各所で感じられた。
ウィーン楽友協会、コンサート: ウィーン交響楽団で曲目はドイツレクイエム。満員でチケットが手に入らず、私たちの切符は立ち見(40シリング)だった。同胞はジーパンで座り込んでいる人も。立ち見は一階平土間の後ろのバルコニー下だった。一度の休憩もなく、まさに体力勝負だった。響いてはいたが、響きの長さは思っていたより感じなかった(バルコニー下だったこともあるが)。全体的に良くまとまった上品なアンサンブルだった。
国立オペラ座、モーツァルト『後宮からの逃走』: 日本でオペラというととても高級な雰囲気がある。しかしウィーンでのオペラはコンサートよりずっと親しみやく、コミカルな演技があったり、とても楽しかった。オーケストラと歌手はどちらも主従の関係ではなくバランス良く共演していた。派手なオペラではないので舞台装置の華やかさ等はなかったが、日本でのオペラにはない洒落た雰囲気を味わったように思える。(石渡智秋 記)
シュロスコンサート: ミラベル宮殿マルモアザール(大理石の間)は、当時モーツァルト一家も演奏していた大広間で、今ではほとんど毎日室内楽やソロコンサートが開かれている。我々がザルツブルグに到着した日は、ベルリンフィルハーモニーゾリステン(フルート、バイオリン、ビオラ、チェロ)の室内楽コンサートであった。その名の通り大理石でつくられた広間は非常に長い響きを生み、弦のアンサンブルに対しては音(特に低音)がこもり、やや聴きにくい感もあった。しかし、サロンコンサートならではの気軽さ、くつろぎを味わうことができたように思う。
祝祭劇場大ホール、コンサート: イースター音楽祭のベルリンフィル演奏会とあって会場は着飾った人で溢れ返っていた。隣席の人に挨拶をしたり、女性を先に座らせるなどという習慣はいたって新鮮である。祝祭劇場は残響時間が短く、幅の広さや天井形状から場所による音の印象の違いが大きい。1階中央では音量不足が感じられ、側壁に近い所では音量は大きいものの、楽器による音のバランスが悪く、ベルリンフィル本来のパワフルで緻密な演奏を聴くことができず大変残念であった。
ガスタイク、コンサート: 音響的にこのホールは今一つという声があるようだが、実際に聴いた印象は今回の旅行の中でもとりわけ良かった。ミュンヘンフィルの音は柔らかく、きれいにまとまったアンサンブルだった。1階4列上手寄りの席で聴いたが、ステージ上の反射板の影響もあったのかもしれない。(小沢あゆみ 記)
早春のブレーゲンツから
ブレーゲンツにはもう春が訪れていた。こぶしが咲き、湖では水鳥が舞っていた。ブレーゲンツはオーストリアの東の端、ボーデン湖畔の町で、ウィーンから列車だと8~9時間もかかる。早朝の飛行機でチューリッヒに飛び、列車でブレーゲンツに入った。
ちょうど6年前、1986年の春、このブレーゲンツの郊外にあるオルガンビルダーのリーガー社でサントリーホールのオルガンの船積み前の式典が行われた。今回は韓国の宣教院のオルガンの式典に参加することとなった。不思議な縁である。宿泊も駅前の同じホテル、すべてが全く変わっていなかった。変わったといえば、湖上音楽祭の出し物である。当時は魔笛であったが、今年は昨年と同じカルメンとのこと。昨年から湖上の舞台が拡張されて、岸辺の観客席とつながった。

野外オペラが出し物のこの湖上音楽祭は、野外オペラにおける電気音響システムの実験劇場としても有名であり、毎年新しい試みが行われている。この音響調整を担当しているのがウイーンの国立歌劇場のフリッツ氏である。
ブレーゲンツに入る前日、このフリッツ氏を国立歌劇場に訪れ、自慢のディジタル調整卓の説明を聞くとともに今年の野外オペラの構想についても話しを伺った。今年からこの音楽祭にもディジタル調整卓が入るとのこと、去年と同じ出し物で新しい音響システムを試みるのだと、彼はこの湖上音楽祭に相当ないれ込みである。なお、昨年のカルメンについてはNEWS91-11号に小口の記事があるので参照されたい。今年はどうなるのだろうか、楽しみである。当事務所では研修の第3グループがこの音楽祭に参加する計画である。
リーガー社の式典はサントリーの時と同じ形で仮組のオルガンを前にして行われた。しかし肝心のオルガン演奏はなく、代わりに二組の楽団によってチロル地方の歌とブラスの演奏が行われた。まさにサウンド・オブ・ミュージックのトラップ一家の世界である。夜は山腹の城を貸し切りで数時間におよぶディナーもあった。わが国の教会では考えられない豪華な一夜であった。
今回の研修ツアーでは、ウイーン、ザルツブルグ、また、ミュンヘンで連夜コンサートを聴くことができた。ザルツブルグの祝祭劇場では待望のショルティ指揮のベルリンフィルを聴くことができたが、香水と宝石で埋め尽されたあの会場はコンサートというより、まったくの社交界である。このオルガン工房に響きわたるチロルの素朴な調べが一番心に沁みた。人と音楽との関わり方について二つの相を見た思いであった。

本の紹介
『オーケストラとは何か』 みつもと俊郎 著 新潮選書
オーケストラといえば現在のクラシック音楽の頂点に立つ存在であるが、ホールに関わり合いをもつ者にとって、あまりにも巨大で掴みようのない音源である。しかし、ここまでに至ったオーケストラの歩みは決して単純なものではない。この“みつもと”さんの本はオーケストラの誕生から、現在のオーケストラ、また、今後のオーケストラの行方などについて、実に広い視野からの論説である。楽器から演奏会場の問題、そして音量や音域の問題など、ホールの設計に関わる重要な指摘もある。
「オーケストラのコンサートに行くと、舞台の上にはいろいろな楽器の奏者が所狭しと座っている姿が目に飛び込んでくる。・・・なぜ、ヴァイオリニストはみんな左側の位置に固まって座っているのか。」・・・「バンドとオーケストラとはどこが違うのか」・・・・こんな調子で本文が始まる。
棒で床を叩いていた指揮の話、舞台が狭く立って演奏していたこと、ピッチもバラバラであった楽器が統一され、指揮者という専門職が生れ、現在のオーケストラが形をなしたのは19世紀になってからであること、オーケストラの経営形態にはプライベート(昔は宮廷、今では企業)所属、劇場付属、国あるいは市の経営という三つがあり、この形態は現在でも続いていることなど身近な話題がふんだんに盛られている。モーツァルトの時代には楽団員には現物給与としてワインの支給があったこと、1839年、ウィーンで行われたハイドンの天地創造に歌手800人、ヴァイオリンだけで120名、計1011名という巨大オーケストラの演奏が行われたなど意外な事実も紹介されている。
ヨーロッパ、アメリカ、日本のオーケストラの紹介の後で、21世紀のオーケストラの姿についての著者の見解が結びとなっている。電子楽器の登場や技術革新が現在のオーケストラをどのように変えるのだろうか、つまり、現在のヴァイオリンやフルートの音色が私たちの感性に何の感動も呼びおこさない日がくるだろうか、あるいは、演奏者のいない電子楽器のコンサートが現在の演奏会以上の感動を与え得るだろうか、などについて著者の思いが述べられている。
NEWSアラカルト
オルガンコンサートのご案内
6月21日(日)の午後3時から東京目黒の白金教会において、西尾純子さんのオルガン演奏会があります。演奏者のプロフィール、曲目の詳細は折り込みのチラシを参照下さい。このオルガンは松崎さん、中里さんという二人のオルガンマイスターによって設立されたマナ・オルゲルバウの製作による2段鍵盤、12ストップののオルガンです。また調律は「ナイトハルトの一番、1724年」というバッハよりも前に案出された平均率とは違った調律法によっています。C-dur、G-durがとくに調和する音階とのこと。西尾さんの演奏をお楽しみ下さい。(注:チラシは東京近郊の方にのみ同封しました。)