
壱岐文化ホールの誕生
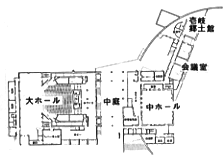

壱岐は玄海に浮かぶ周囲80kmの島で、対馬とともに九州と大陸・朝鮮半島を結ぶ国境の島として、魏志倭人伝にも登場するという。数年前には、卑弥呼伝説にまつわる遺跡発掘で話題を集めた。また、玄界灘の海産物(特にウニ)と麦焼酎も有名である。行政区分上は長崎県に属しているが、地理的には福岡に近く、福岡空港からYS-11 で30分、博多港から船で1 ~2 時間の距離にある。島は、郷ノ浦・石田・芦辺・勝浦の4 町からなる。壱岐文化ホールは、最も人口の多い郷ノ浦町の合併40周年を記念して、町の文化活動のみならず、壱岐全体の活性化と地域交流の拠点として計画された。総事業費48億円は、町の年間予算のほぼ半分にあたるという。渋村町長は日経アーキテクチュアの中で、「壱岐の高校を卒業する500 人の生徒のうち、島に残るのは10人。これが過疎の現状だ。コンベンションで人を集めて島の過疎をくい止めたい。施設のないところに人は集まらない。」とホール建設に込めた熱い思いを語っておられる。
プロジェクトは、建設計画全体をまとめる宗本順三・京都大学教授のもとに、教授の主宰するラウムアソシエイツと福岡の那の津壽建築研究所、構造の小堀鐸二研究所、家具設計の西邨正貢氏ほか、われわれも参画して進められた。ホールは、町の中心に近い小高い丘陵に囲まれた傾斜地に位置している。中庭をはさんで1000人規模の大ホールと最大で600 人収容の中ホールが配され、その奥に壱岐郷土館ほかのコミュニティー施設が連なる。さらにその先は、古くからの湧き水” 常磐井(ときわごう)を復活させた親水公園へと続く。正面から望むコンクリートの大庇と中ホール・郷土館を包む円弧壁の力強さと、その上の柔らかい曲面金属屋根との対比がおもしろい。筆者には、大海原に優雅に浮かぶ鯨に思える。
大ホールは、600 席の主階席を400 席の2 階席が取り囲む形式で、少人数のイベントにも対応しやすい配慮がなされている。壁・天井はモノトーンの色合いで、特別にデザインされた椅子の色のランダムな配置がアクセントとなっている。設計は、講演会・集会などのコンベンション機能を主用途とする多目的ホールとしてスタートした。クラシックコンサートなども開きたいという利用者の要望で、まず最初に、舞台反射板を設けないでも、何とか生音に良い音響条件が作り出せないかとの相談を受けた。有効な反射音を得る上で音源まわりの反射面は特に重要である。反射板を兼ねた防火シャッターを下ろした前舞台の形式も考えられないことはないが、やはり本舞台内に反射板を組むのが一般的であろう。島内の小ホールにはいずれも反射板が設備されていなかったこともあって、反射板の設備を強く勧めた。発注には間に合わなかったが、追加措置で質の高い舞台反射板が設置されることとなった。ホールの残響時間は、主用途がコンベンション機能であることを考慮して、中庸な長さとした。反射板設置・空席時の中音域における測定結果は、1.7 秒である。
中ホールは、カラフルな壁面と位相差のあるサインカーブ天井が、楽しい空間を演出している。講演会、展示会や結婚式など、身近な各種イベントを想定した平土間のスペースである。残響時間は空室時、中音域において1.8 秒である。
ホールは今年2 月に、新結成の郷ノ浦太鼓でお披露目をした。残念ながら実際の催し物には、まだ立ち会っていない。機会をみて是非また訪れてみたい。今各地でホールの専門化が進んでいるが、離島であり限られた人口・財政規模のこの島に、日本型多目的ホールの存在意義を強く感じるプロジェクトであった。(小口恵司 記)
コンサートホールの音は変わる?
サントリーホールがオープンしてこの秋で10周年を迎える。オープン当初、特に東京のオーケストラなどからステージ上での演奏のしにくさなどが伝えられたが、数年経った頃からはそのような声もあまり聞かれなくなった。実際に客席で聞くオーケストラのアンサンブルもかなり良くなってきた。ステージの上で自分の音や他の楽器の音が聞こえにくかったら良いアンサンブルにはならないのは当然のことであろう。東京のオーケストラの人達に聞くと、最初は慣れなくてステージ上での聞こえ方がよく分からなかったが、しばらくして慣れてくるとお互いの音も聞こえるようになってきたとのことである。
ホールの音が変わったという意見も多数あった。筆者自身も実際にコンサートを聞いていて客席でそのように感じたこともある。ホールに何か手を加えて音響を改善したのであろうと色々な人からいわれたが、実際に音響に関する改修などは一切していない。当初は演奏者が慣れてきて、アンサンブルも良くなりそのように感じるのであろうと思っていた。しかし、それだけでは説明しきれないようなこともしばしばあった。
昨年の6月、シカゴ交響楽団のサントリーホール公演終了後、指揮者のバレンボイムを楽屋に訪ねた時、会うなり「このホールの音響の何をどう変えたのか」と問い詰められたことがある。現在、シカゴ響の本拠地のシカゴオーケストラホールの改修計画が進行中であり、バレンボイムが特にこうしたことに敏感になっていたのかもしれない。いきなりで思いもかけない質問であったので「音響的には何もさわってませんが、演奏者もここの音響に段々慣れてきたようですし…。」としどろもどろに答えると、すぐさま「シカゴ響に関しては、このホールで慣れるほど演奏していない。」と返されてしまった。バレンボイムはサントリーホールオープン以来、ピアノ独奏者として、パリ管弦楽団の指揮者として、そしてシカゴ響の指揮者として度々訪れており、このホールの音響特性をよく知っているのである。彼によるとステージ上で以前よりクリアーによく聞こえるようになったという。「ホールも楽器と一緒で、使っているうちに段々馴染んでよく鳴るようになります。」というと納得してくれた。
1963年にオープンしたサントリーホールの兄貴分ともいうべきベルリン・フィルハーモニーホールもオープン当初は音響の点に関して様々な問題点が指摘されていたが、やがて数年のうちに改善されて良くなったといわれている。このホールの音響設計を担当された故ローター・クレマー博士(当時ベルリン工科大学教授)が数年前に他界される少し前に、ミュンヘン郊外のご自宅にお訪ねしてお会いする機会があった。以前から機会があればお聞きしたいと思っていたので、思い切ってベルリンのホールでどのような音響改修をなされたのかを伺ったところ「何もしていないよ」と笑いながら答えられた。
この「ホールの音、響きが変わる」ということは、音楽家、演奏家の間ではしばしば経験的に当然のように語られていることである。しかしながら、その物理的な意味あいが明らかにされているわけではなく、音響の学会レベルにおいては未だ真正面から議論されていないテーマである。もっと身近な例としては楽器も同様である。新しいうちは鳴りが悪いが弾き込んでいくうちに段々鳴るようになるという事実である。これも楽器を演奏したことのある人には経験的によく知られていることであるが、そのメカニズムはホール同様、学会レベルでは未だ明らかにされていない。
京都の新しいコンサートホールがオープンしたのは昨年の10月である。当初より素直でバランスの良い響きであったが、ホール全体にわたっての響き方については今ひとつ大人しい感じで、もう少しダイナミックに響いて欲しいという思いがあった。これも数年も経てばもっと良くなるのかと考えていたのであるが、半年後の今年3月に3ヶ月ぶりに聞いて驚いた。オープン当初の音とはかなり違っていてホール全体が響くイメージがかなり出てきて以前よりずっとライブに感じた。この点については指揮者や評論家の方々の意見も一致しており、地元オーケストラである京都市交響楽団のメンバーもホールの響きが半年のうちに段々と変わってきたことを指摘している。感覚的にはサントリーホールにおける3年分位の変わり方が京都ではわずか半年で起こった感じである(変わり方は違うようであるが)。京都でもすでに音響の改修が行われたとのまことしやかな噂が持ち上がっている。このように簡単に音響の改修が出来るものならば、我々としてはもっと積極的に行いたい位である。この京都でのホールの音響の変わり方は非常に短期間でのことであり、他のホールの場合と違って分かりやすかった。この位変化するとホール完成前後における音響調整は何の意味も持たないのではないかと思われる程である。
ホールの音響が年月が経ち使い込まれていくうちに変わっていく理由については、様々なことがいわれている。完成したばかりのホールは湿気が多いがそれが次第に乾いていくというもの、ホールの内装が振動を繰り返すことによってより振動しやすくなるというもの、等々であるがいずれも意見の域を出ない。クラシック用コンサートホールの歴史はわが国ではまだ浅く、我々自身も勉強している最中である。しかし、ホールの音響が完成後大なり小なり変わっていくことがあるという事実は認識しておく必要があろう。幸い、これまでのホールはいずれも音が良くなる方向に変わってきている。(豊田泰久 記)
本の紹介
How They Sound CONCERT AND OPERA HALLS L.Beranek著 アメリカ音響学会刊
著者のベラネク先生はアメリカ音響界の大御所、数々の著書がある。なかでも、リンカーンセンターの設計時の資料をもとにまとめられた、MUSIC, ACOUSTICS & ARCHITECTURE(1962年)は当時の世界のコンサートホール、オペラハウスを対象に、その建築、音響特性、それに評価までを加えた異色の著書で、建築音響関係者のバイブルとして今日でも利用されている。本書はその第2弾にあたるもので、21ヶ国、76ホールの建築、音響、評価が紹介されている。わが国では東京文化会館を始め7ホールが取り上げられている。
本書はクラシック音楽の歴史とホールとの関係から始まる。音楽愛好家には楽しい章である。ついで、室内音響効果に関する評価量のまとめがある。また、音響効果の点数評価(レーティング)について、ベラネク先生独自の方法の提案もある。コンサートホール、オペラハウスの設計の考え方も述べられている。写真、データも豊富な646ページの大著、見ているだけで世界のホールに遊ぶことができる。それに、わが国のホールをベラネク先生がどのように評価されているのか、先生のホール音響についての姿勢を知ることもできる。
なお、ベラネク先生は、浜離宮朝日ホール、新国立劇場の音響設計者でもある。
本書は東京駅八重洲口の八重洲ブックセンター洋書売場で入手できる。定価6,000円、住所は中央区八重洲2-5-1、Tel:03-3281-3606, Fax:03-3281-7781である。(永田 穂 記)
君に伝えたいビジネス行動原則98 佐藤和明 著 実務教育出版 1,300円
著者の佐藤和明さんは本NHKのアナウンサー、音響機器販売会社を経て、1979年プロオーディオ機器の専門商社、音響特機株式会社を創立、1985年、60才を機に社長を退き会長に就任というダイナミックなご経歴の経営者である。その間、音響特機株式会社は年商20億という規模に発展、現在プロオーディオ機器の商社として業界トップの座にある。
佐藤さんは数年まえに、自社の社員教育用として「仕事の基本」という新書版のテキストを出版された。佐藤さんの記事の特徴は具体的な事例を出発点として精神を述べるという内容にある。たとえば、電話の掛け方一つにしても、ボーズ社の佐倉さんというこれまた音響業界知る人ぞ知るという経営者の電話応答を例にとってマナーを説いている。
本書はこの「仕事の基本」を充実、発展させ、一般ビジネスマンを対象に日常の行動原則をまとめたものである。電話のマナーから、社内コミュニケーションの技術、文書の書き方、情報管理の要点、営業活動の具体的な方法、クレーム処理から決算書の読み方まで、佐藤さんが社長職をとおして、身を挺して学びとられた行動理念が98の項目にまとめられている。たとえば、“悪い情報ほど報告は緊急”、“クレームは天の声”、“情報の私物化を徹底的に追放する”等々、鋭い指摘がある。
とかく、このような分野についての教育の場をもたないわれわれのような小規模集団の職員には格好のビジネス指導書である。(永田 穂 記)